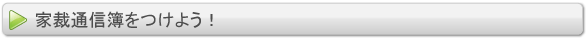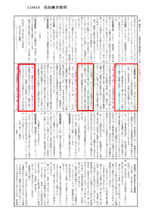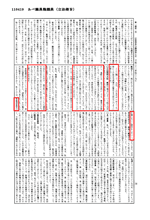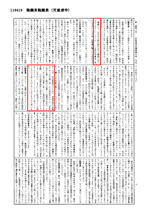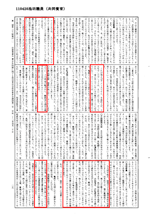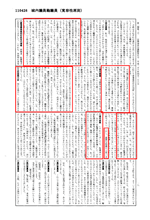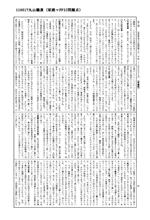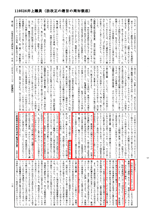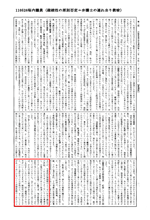トップ » 家裁通信簿をつけよう
2011年4月28日に衆議院で、そして5月27日に参議院でともに全会一致で可決した民法の一部改正案は、その後6月3日に公布されました。親の虐待から子どもを守るため、「親権を最長2年間停止させることを可能」にし、民法766条は下記のように、「離婚の際は、子どもの利益を優先させ、子どもとの面会交流や養育費を定めること」が明記されました。
| 民法766条 | |
|---|---|
| 改 正 前 | 改 正 後 |
| 1.父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。 2.子の利益のため必要があると認めるときは家庭裁判所は子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。 3.前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更は生じない。 |
1.父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 2.前項の協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同事項を定める。 3.家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。 4.前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 |
では、「子の利益」とは何をさすのでしょうか?
これについて、江田法務大臣は衆議院法務委員会で、「(父母が高いストレス状態であったとしても)親と子というのは大切な関係だから、面会交流を子の利益のため、子の福祉のため是非実現するように努力をしようということが家庭裁判所の調停、審判における方向だとこの法律は示している」等と回答しています。
これまで調停や審判で面会交流を制限するとして頻繁に使われてきた、「小さなお子さんはお母さんといる方が子どもに利益にかなっている」、「監護親のストレスになるから面会交流は時期尚早」、「子どもが会いたがっていないのだから会わす必要がない」等の理由は、今後使えないことになります。
豊澤最高裁判所長官代理は、今回の民法改正について、「随時各裁判所に対して周知を行ってきた。今後更に法改正の趣旨を踏まえた事件処理が図られるよう、必要な情報の周知に努めていく」と発言しています。
しかし、現場の家庭裁判所では知られていない、酷い場合には、知っていても無視している可能性があります。
調停委員や調査官がおかしなことを言ったら、下記議員の国会での質問や、江田法務大臣の答弁を積極的にアピールしていきましょう。
しかし、現場の家庭裁判所では知られていない、酷い場合には、知っていても無視している可能性があります。
調停委員や調査官がおかしなことを言ったら、下記議員の国会での質問や、江田法務大臣の答弁を積極的にアピールしていきましょう。
最高裁家庭局からの民法等の一部を改正する法律の
公布等についての通知(平成23年6月6日付)
最高裁家庭局からの民法の立法趣旨理解を促す通知
(平成23年8月6日付)
民法が改正されて、家裁が本当に変わったのか評価していく必要があります。一般企業の場合は、ユーザーが企業を意識的に、あるいは無意識のうちに評価することで、自浄作用が働きます。しかし、裁判所の場合はそうはいきません。家裁ユーザーである当事者が自らで評価し、公表していくことでしか、その実現をみません。
あってはならないことですが、もし民法改正前後で家裁が変化をしていないのであれば、それを立法府である国会に報告することができます。できるだけ多くのサンプル数で、説得力あるデータにしましょう。
【通信簿の目的】
「通信簿」は、民法766条の改正の趣旨が家裁(その他の裁判所も含む)で適切に運用されているかどうか、それを法務大臣の答弁等に照らし合わせて評価するものです。結果は統計的に処理し、プライバシーは厳守いたしますので、ご協力ください。評価結果は、「通信簿を見る」で定期的に更新するほか、国会議員やマスコミに対し、データを提供していく予定です。
【通信簿のつけ方】
本通信簿では、非監護親の子どもとの面会交流について、家裁(その他の裁判所も含む)の運用を評価します。調停/審判/裁判を区別し、面会交流申立て、監護者指定、離婚裁判などの事件の種類も区別して評価していきます。例えば、面会交流の調停、面会交流の審判などと評価対象を選択してから、評価することになります。
評価対象が複数ある方は、その数だけ通信簿をつけることが可能です。
【所要時間】
約20分です。

あってはならないことですが、もし民法改正前後で家裁が変化をしていないのであれば、それを立法府である国会に報告することができます。できるだけ多くのサンプル数で、説得力あるデータにしましょう。
【通信簿の目的】
「通信簿」は、民法766条の改正の趣旨が家裁(その他の裁判所も含む)で適切に運用されているかどうか、それを法務大臣の答弁等に照らし合わせて評価するものです。結果は統計的に処理し、プライバシーは厳守いたしますので、ご協力ください。評価結果は、「通信簿を見る」で定期的に更新するほか、国会議員やマスコミに対し、データを提供していく予定です。
【通信簿のつけ方】
本通信簿では、非監護親の子どもとの面会交流について、家裁(その他の裁判所も含む)の運用を評価します。調停/審判/裁判を区別し、面会交流申立て、監護者指定、離婚裁判などの事件の種類も区別して評価していきます。例えば、面会交流の調停、面会交流の審判などと評価対象を選択してから、評価することになります。
評価対象が複数ある方は、その数だけ通信簿をつけることが可能です。
【所要時間】
約20分です。