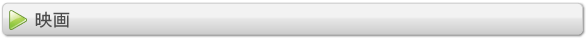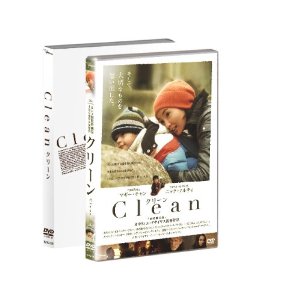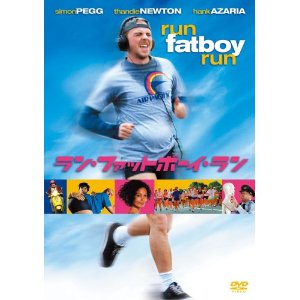映画『事実無根』
いつ誰に降りかかるかもしれぬ「事実無根の罪」、どこの家にも潜んでいる「家族の問題」。これらが複雑に絡み合い翻弄される父娘の姿を、京都に実在する一軒のユニークな喫茶店を通して映し出す。長い間止まったままの家族の時間・・・。しかし「事実」より大切なものに気づいた時、人生の時計の針は再び動き出す──

映画『 幼な子われらに生まれ 』2017年8月26日(土) 全国公開
映画『 幼な子われらに生まれ 』2017年8月26日(土) 全国公開
「やっぱりこのウチ、嫌だ。本当のパパに会わせてよ」
——娘に言われたとき、妻には新しい命が宿っていた。
「普通の家族」を築けない、不器用な大人たちの愛すべき物語。
映画公式サイト http://osanago-movie.com/
試写会のトークイベントに参加いたしました。
https://youtu.be/Hl7UUJv00hw
フル・モンティ
【ストーリー】
かつては鉄鋼業で賑わったイギリス北部のシェフィールドは、今では失業者の溢れる寂れた姿をさらしていた。そんな失業者の一人ガズは、離婚したマンディとの間の幼い息子ネイサンの養育費700ポンドを払う事が出来ずいた。いつもネイサンに泥棒の方担ぎをさせたり、汚い言葉を吐き、大人になりきれないガズに業を煮やしたマンディは「養育費が払えないなら単独親権の裁判を起こす」と言ってきた。
そんな折、たまたま町に興業で来ていた男性ストリップショーに女性陣が熱狂するのを見たガズは、親友のデイヴと共に何の取り柄もない自分たちでもストリップをすれば金を稼げるのではないかと考えた。
排気ガスで自殺しかけていたロンパー、社交ダンスが得意な元上司ジェラルド、50歳オーバーだがリズム感に長けた黒人ホース、立派なイチモツの持ち主ガイをなんとか仲間に加え、さっそくストリップの練習が始まるのだが……。
【感想】
西欧諸国には親権や養育費など、子どもと父親に関する家族法の問題に関心を持つ社会運動を行う、伝統的で大きな父親の権利団体がいくつかある。中には相当過激なキャンペーンを行うグループもあるようだ。
彼らの主張の一つは養育費の問題があげられる。
高額な養育費は、「母親の離婚への経済的な動機づけになりかねない状況で、父親が子どもと過ごすための余裕を残さない」あるいは、「母親が再婚を繰り返したり、お互いの経済状況が変わった場合に養育費の見直し」などが問題とされている。
フル・モンティの主人公ガズは鉄工所の倒産で職にあぶれてしまい、700ポンドもの養育費を払えない状況にある。元妻は「私たちの工場で製品検査をすれば時給2ポンド50セント払う」と提案する。そうしなければ子どもとは会わせないと。
そこでガズは悪友たちと、自らがストリッパーになって大金を稼ごうとするのだが、当のガズはガリガリのやせっぽち、親友のデイブは肥満体。ダンスのレッスンに泣きついた元上司もおっさん…といった具合。どう見ても見栄えはしない(笑)。練習に付き合わされる息子のネイサンもバカバカしいやら、情けないやらで「もうお父さんには会わない」と飛び出してしまう。しかしガズは「父さんはバカか?お前を愛してるんだ。これからも大好きなお前に会うためにはコレしか方法はないんだ!」息子に訴えた。父親が自分のためにそこまでするのかと気付いたネイサンは以後、会場費の前払い金100ポンドを自分の貯金から切り崩すように父親を説得するなど、父親を応援するようになる。
ヘンテコな展開のコメディだし、父親のガズも体裁を取り繕うばかりで、仕事もロクに探さないダメ男だが、それでもなんとか息子との関係をキープしたいという熱意だけは涙ものだ。
最後にショーが始まるシーンで、土壇場でガズが「女性客だけって言ったのに、何で男がいるんだよ!」と出演を拒否する場面がある。グズグズする父親に向かって「男だろ、自分が言いだしっぺのくせに仲間を裏切るのかよ!つべこべ言わずに行けよ!」とネイサンは背中を押す。
面会が長く続く場面では、こんな風にいつも疑問がわく時がある。母親からは養育費の請求、逼迫する生活、それでも元妻から感謝の一つも聞こえてこない。周囲からも「もう諦めて次にスイッチしろよ」なんていう知人も出てくる。このままでいいのか?諦めそうになる時もあるけれど、このガズとネイサンのように、愛情さえ伝われば、いつか子どもの方から「ガンバって」と言われる時がくるんじゃないかな。
肉体的に子どもを宿す母親と違って、男は「子どもが生まれたから即父親」になれるわけではないと、なにかの本で読んだことがある。育っていく子どもと関わることで、少しづつ父親の強さや寛容さを身につけていくのだと。
いつか自分がちゃんと父親として子どもに向き合った時には、丸裸(フル・モンティ)でも堂々としていられるように、自分の中の父性を育てていきたい。
クレイマー・クレイマー
【ストーリー】
テッド・クレイマーとジョアンナ・クレイマー夫妻は結婚8年目を迎え、一人息子ビリーも7歳となっていた。家庭を顧みずに仕事優先の生活を送るテッドに不満を募らせていたジョアンナは自立を決断し、家を出て行ってしまう。
いままで、家事や育児は妻に任せっきりだったテッドは、ビリーの朝飯さえ作れない。しかし、やがて家事にも慣れ、希薄だった息子との絆も深まってきて一年半ほど経ったある日、突然ジョアンナが養育権を訴えてくる。家事と育児の両立で仕事に支障をきたして失業したことも重なって、ついには裁判で養育権はジョアンナ側に…。
【感想】
今回、ベタベタな親権テーマの金字塔である本作品を紹介するのは、テッド役のダスティン•ホフマンが初監督作品となる『カルテット!人生のオペラハウス』が日本上陸して話題になっているから…というのはこじつけで、我々の問題を語る上で欠かせないこの作品を、いつか書こうと思っていたものの、大作であるがゆえに、なかなか書けないでいたのを、ここぞチャンスとばかりに紹介します。
「紹介します」などといっても、もちろんご覧になっている方多いことでしょう。
7歳のビリーが慣れない父子生活で、母親の写真を抱えて「ママに会いたいよ!」と泣くシーンは、涙なしには見れません。また、裁判の結果、父親と離れて暮らすことになった息子に「愛してる。会えなくなるワケじゃないんだ」と説得するシーン、「パパもいなくなっちゃうの?」と怯えるビリーにキスするシーンなど、胸の痛さに息が苦しくなる想いです。
1980年代のアメリカでは、60年代から始まったウーマンリブ運動も定着し、その反動というのか、逆に男性の権利や、家庭における父親の役割が見直され始めてきた時代です。やっと女性差別撤廃条約が締結されたばかりの当時の日本で、「自分の自己実現の為に家族を放り出した妻」ジョアンナはどう映ったのでしょうか。
私自身、テッドと同性の親として、息子に「(愛しているけど)もう一緒には暮らせない」と手紙で書いてきて、息子を酷く傷つけておきながら、自分が都合よくなったら「やっぱり一緒に暮らしたい」と言いだしたり、大人の二人がお互いの意思で結婚して、お互いの了解で離婚したのに「失敗したのは全部、元夫のせいだ」と裁判で話す彼女の稚拙な無責任さなど、テッドに同情してしまいますが、この映画、よく考えると、引き離しを行っているのは旦那の方です。
かつては妻が精神的に追い詰められるほど、妻の意思や個性を無視して家事人形のように扱ったDV夫が、泣く泣く出ていかざるを得なかった妻に「勝手に出て行ったんだから、息子に会う権利はない!」というワケなんですから…、アレ? どっかで聞いたような話になってきましたね。
でも、そこは映画なので、お互いを傷つけ合う裁判を介して、それでもお互いがそれぞれに息子のことを愛していることを理解しあう様が美しく描かれています。
テッドは法定の証人席に息子を座らせて、両親の醜い罵り合いの真ん中に立たせることを拒否したし、ママの悪口もついぞ言葉にしていません。弁護士が、公園でビリーに怪我をさせたのは「父親としての能力の欠如だ!」と訴えた時、ジョアンナは「ごめんなさい。そんなことは思っていない」と謝ります。結局、「大岡裁き」じゃないですが、監護裁判に勝って息子と暮らすことを許されたはずの元妻ですが、父子を引き剥がすことで息子が受ける痛みを慮って諦めます。
裁判所の指示では、非監護親になるテッドには「隔週末の宿泊と、平日週一日の食事、長期休暇の半分」の時間しか(敢えてココでは“しか”という)与えられなかったけど、映画の最後でお互いの「ビリーに対する愛情」を理解し、尊重し、本当の意味で息子にとっていいことをしようと考えた両親なら、ビリーは好きな時に父親とも、母親とも会って、自分に向けられる愛情を感じられることでしょう。
さて、最後に、テッドがビリーとの別れを覚悟した朝のメニューにと、二人で作ったフレンチトーストのレシピをご紹介しましょう。これは個人的な持論ですが、料理を共同作業するということは結果のイメージを共有し、その過程をともに歩むことであり、二人の距離を縮める助けになると思います。
[材料]
•卵 2コ
•牛乳 120cc
•バター 適量
•食パン 3枚
[作り方]
① 卵2コをボールに割り入れ、フォークで息子にかき混ぜさせる
② ①に牛乳を入れて、今度はお父さんが手早くかき混ぜる
③ 息子に食パンを3枚出させている間に
④ フライパンをコンロで熱し、フォークでバターをしく
⑤ 食パンを2.の卵液に浸して、一枚ずつフライパンで焼く
⑥ここでフライパンを床に落とすと、最初のダメパパになるので注意しながら皿に盛る
※食べるシーンがないのですが、砂糖を卵液に入れていないので、皿に盛ったらハチミツかジャムをかけてもいいかもしれません。
「さぁ、こいつを平らげよう」と、子どもをハグしたら、もう気分はダスティン•ホフマンですね!
マネーボール
【ストーリー】
選手からフロントに転身し、若くしてメジャーリーグ球団アスレチックスのゼネラルマネージャーとなったビリー・ビーンは、自分のチームの試合も観なければ、腹が立てば人やモノに当たり散らす短気で風変わりな男。
ある時、ビリーは、イエール大学経済学部卒のピーターと出会い、彼が主張するデータ重視の運営論に、貧乏球団が勝つための突破口を見出し、周囲の反対を押し切って、後に“マネーボール理論”と呼ばれる戦略を実践していく。
当初は理論が活きずに周囲から馬鹿にされるが、ビリーの熱い信念と、挑戦することへの勇気が、誰も予想することの出来なかった奇跡を起こす!!
【感想】
せっかくの目利きで仕入れた選手を大事に育ててきたのにその選手が大きな成績を残すと金持ち球団に奪われてしまい、かといって優れた選手を迎え入れるような金銭的余裕もなく、八方ふさがりな状況の貧乏球団アスレチックス。
しかし、ゼネラルマネージャーのビリー・ビーンは諦めずにスター性に乏しく他球団からは魅力的に映らないものの、出塁数は稼げる選手を集めて数字で勝つという新しい理論にチャレンジする。
最初は、仲間からの理解を得られずにチームは低迷するが、やがて崖っぷちで選手や監督陣を熱く口説いて、ついには結果を残す。
「大きな敵にチャレンジする逆転劇」「信じるものを貫く根性」。
熱いじゃないか! なんだか自分の仕事を翻って、「よし、明日からガンバるぞ!」という気にさせてくれる映画だ。
すでにネタばれ気味ではあるが、主人公ビリー・ビーンには別れた奥さんとの間に12歳の娘がいることになっている。
元妻とその新しい旦那と一緒に住んでいるわけだが、同じオークランドに住んでいるらしく、たびたび娘と会うシーンがある。
この娘役ケリス・ドーシーの歌う歌がとても美しくてちょっと涙を誘う。
彼女がギターで弾き語りする歌詞は、「パパ、わたし一人でまよっているの」。
それにしても、娘が携帯電話を持っていることを知ると「この歳には早くないか?」と新しい旦那の前でビーンが元妻に忠言すると、「あら、何かあったら大変と思って持たせているのよ」と元妻が応えるシーンがある。
「そうそう」と新しい旦那が相づちを入れると「あんたは黙ってろ、これは彼女とオレの問題だ」というビーンが吼える。
つまり娘の教育、養育、監護にかかわることは明らかに遺伝的な両親の責任だというわけだ。
これが10年前のアメリカでは常識なのだろうか?
だとしたら、現状の日本とあまりに違う「常識」に羨ましい限りだ。
ビリーのチームは優勝こそしなかったものの、連続20連勝という歴史的な記録を打ち立てた。
その成功を手にして、ビリーにはインディアンスから破格のヘッドハンティングをうけることになる。
しかしインディアンスの本拠地はオハイオ、カルフォルニアからは遠くはなれている。
そうして娘からのCDを聞きながら、ビリーは考えて、そしてそのオファーを断るシーンがある。
仕事か。
別れた妻といる娘か。
どちらを取るのが正しいとは決して言えないと思う。
妻と別れた理由には映画では触れないが、その選択も結局まったく自分に非がないわけじゃないだろう。
結局、ビリーは古巣の世話になった球団と、娘を選んだ。
永遠を誓う伴侶に出会えることが人生の大きな影響を与えるように、離婚だってそれにともなって無傷ではいられない。
夫婦がそれによって人生になんらかの足かせをはめられるのは、結婚という人生を選んだ時点で当然の責任だと思う。
ただし、その二人の間に生まれた子どもは本当に純粋な被害者だ。
たとえばそれを子どものせいにして「お前がいたから諦めた」と責任転嫁するような親ならば、子どもと離れて生活するのも1つの選択だと思う。
また、世界を変えるような仕事と天秤にかけるのも難しい選択だと思う。
ただ、そのいずれの場合でも、やはり子どもは両親に見守られながら大人になるのが理想的というは1つの方向性だ。
でも、今の僕にはこの方向性を手放す他の選択肢、他の価値観が見当たらない。
たまにしか会えない息子の無邪気な笑顔や、「おとーしゃん!」としがみつく小さな腕に匹敵するような価値を、残念ながら今の仕事に見いだせない。
いつか、そういうことが見つかることがあるかもしれないが、今は、本当に彼のそばで彼の成長をサポートしてあげたいと思う。
そういう意味でも、なんだかビーンの物語と、娘の歌う歌詞に涙しちゃったのかもしれないな。
クリーン
【ストーリー】
往年のロックスター・リーを夫に持つエミリーは二人の間の息子をリーの父親の住むバンクーバに預けて、仕事とクスリに依存していた。あるとき、リーが薬物の過剰摂取で死亡。エミリーも麻薬所持で逮捕されてしまう。半年の刑期を経て、リーの父親に会うエミリーだが、そこで父親に言われたのは息子のジェイは自分たちが育てるので、しばらくは会わないで欲しいという申し出だった。
【感想】
刑務所を出てからもしばらくは薬物にすがるエミリーだが、息子に会いたい一心で生活を改めることを決意する。パリに住んで、仕事を見つけた彼女は息子を監護するリーの父親宛に手紙を書く。たまたまリーの母親、つまり息子ジェイの祖母の病気の検査でロンドンにきていた義父は母子を会わせようと試みる。
つまり、母子を引き離そうとしているのは息子を殺されたと思い、恨みに思う義母の方なのだ。義母は孫に「お父さんを殺したのはお母さんだよ」と吹き込み、それを信じる息子はパリまで祖父につれてこられるが母親に会うことを拒否する。一方、やっと息子と会えると思って喜んでいたエミリーは失意で泣き出してしまう。「私だって努力したんだ」という義父に「ダメならこんなに期待させないでほしい」と泣くエミリーの気持ちは痛いほどわかって、ついこちらも涙ぐんでしまう。
一度は悲しみのあまり飛び出してしまうエミリーだが「人間は変われる」「私は病気の妻を傷つけたくはないが、年寄りがいつまでもジェイを面倒見れるとは思えない」という話を聞いて、勇気をもって息子と対面することを決意するエミリー。
息子に会いたい。でも嫌われたらどうしようという恐怖。
そうして、ぎこちない再会を果たす。
最初は構えていた息子もやがて少しずつ気持ちを開いていく。
この映画では、エミリーの義父になるアルブレヒトが理解のある人格者で、孫も、また引き離しを続ける妻も愛しているのがよくわかる。そうしてどうするべきかを冷静に考えている。
アウトローや、薬物摂取を、どことなくカッコいいものに仕立てる嫌いはあるし、あまりにも簡単に解消される母子の葛藤は現実感がないけれど、アルブレヒトの優しく暖かい言葉に気持ちが癒される気がする映画だった。
ラン・ファットボーイ・ラン
【ストーリー】
出来ちゃった婚のリビーを結婚式会場に置き去りにして逃げ出した超無責任ダメ男のデニス。それから5年、5歳になった息子ジェイクとの面交を重ねながら、なんとかリビーとジェイクとの生活を取り戻したいデニスだったが、そんな折、リビーの新恋人、お金持ちでハンサムのアメリカ人ウィットンが出現。
自分の誠意を見せるために、マラソン好きのウィットンに張り合ってロンドン・マラソンに参加することになるが・・・。
【感想】
責任感に耐え切れず、妊娠中の新婦を置き去りにして逃げ出す超ダメ男のデニスだけれど、5年後シーンでもリビーは恋人がいても「子どもには父親は必要よ」「パパはお母さんが結婚してもパパだから」と息子のジェイクや、デニスに話すシーンがある。1つはリビーが本当に子どもを愛する母親であること、
もう一つはイギリスの法的な事情もあると思う。
イギリスは欧州各国の中でも、離婚率が高い国になっている。女性の社会進出も目覚しく、「経済的に自立する女性」も日本の比ではない。もともと個人主義の国なので、子どもも社会に出れば自立することを基本としている。いつまでも親元を離れない日本人とは大違いだ。
それでも気になる離婚後の親権については、やはり共同親権ということだ。ネットで調べていると、2007年にブレア首相からブラウン首相に交代すると
「児童、学校および家庭省」という省が編成される。そして「イギリスを子どもと若者が育つ上でもっとも最良の場所」にするべく様々な改革がなされているらしい。
実は2000年代前半に起こった凄惨な児童虐待がシングルペアレントの家庭で起こったことに起因しているというのもあるようだ。
映画の中のデニスとリビーが結婚式前に籍を入れていたのかどうかは知らないが、今では未婚の場合でも、子どもの出生届には二親揃って出生届けを出すことが義務付けられているのかな?というような記事もあった(が、調査が不十分なので確信はないけど)。
これは、毎年4万件を越す片親のみの出生届けに対し、父親の責任を喚起する意味もあるらしい。
イギリスの映画を見ていると、けっこうこうした離婚後の子どもをめぐる親子の諸々や、母親と暮らす息子の相談を聞く父親なんてシーンをけっこう見かける。そして、そういうお父さんは、どうも人生落伍者的なヤツが多いんだけど、
でも子どもをすごく愛してる憎めない大人こどもに描かれている。
そういうダメなお父さんを見ていると、つい自分と重ねてしまうけれど、イギリスの場合、それでも子どもとは頻繁に会えるのに日本ではそうはいかないお国柄に、どうしても憂いてしまう。
「八日目の蝉」
「八日目の蝉」オフィシャルサイト
【あらすじ】
1995年10月東京地裁。秋山丈博(田中哲司)、恵津子(森口瑤子)夫婦の間に生まれた生後4カ月の恵理菜を誘拐し、4年間逃亡した野々宮希和子(永作博美)への論告求刑が告げられた後、希和子は静かにこう述べた。「四年間、子育ての喜びを味わわせてもらったことを感謝します」と……。
希和子は妻帯者の丈博を愛し彼の子供を身ごもるが、産むことは叶えられなかった。そんな時、丈博と恵津子の間に恵理菜が生まれたことを知った希和子は、夫婦 の留守宅に忍び込み連れ去ってしまう。赤ちゃんを薫と名づけ各地を転々としながら、流れ着いた小豆島で母と子としてのひと時の安らぎを得る。美しいその島 で 、薫に様々なものを見せ体験させたいと願う希和子だったが、捜査の手は迫り、フェリー乗り場で4年間の逃避行は終わりを迎える。
恵理菜は4歳で初めて実の両親の元へ返されたが、家族の再統合は叶わず、自分を誘拐した希和子を憎むことで本当の気持ちを封印し心を閉ざしたまま、大学生(井上真央)となり家を出て一人暮らしを始める。そんな折、岸田(劇団ひとり)に出会い、妻子ある岸田の子を身ごもる。
ある日アルバイト先に、誘拐事件について書きたいというルポライターの千草(小池栄子)が 訪ねてくる。心を閉ざして生きる恵理菜の生活に立ち入ってくる千草に励まされ、恵理菜は希和子との逃亡生活を辿る旅に出る。小豆島に降り立った時、恵理菜 は記憶の底にあったある事実を思い出し、封印していた本当の気持ちを千草に打ち明け、お腹の子への母としての愛を確認する。
【当事者視点】
子どもと引き離された当事者であれば誰しも、ラストシーンで恵理菜が今まで一度も口にすることができなかった本当の気持ちを話すシーンに涙するでしょう。
大人たちの身勝手な行動に振り回され傷付くのは子どもなのだということ、こんなにも深く長く苦しめてしまうのだということを改めて感じ、胸が締め付けられます。それに対して今の自分の無力さが悔しくて、いろんな感情が入り混じった涙が止まらず、映画が終わった後もすぐには動けませんでした。
一旦離れてしまった家族が再統合することの難しさも描かれています。4歳 で戻ってきた我が子とうまくいかず、ヒステリックになってしまう実の母、恵津子…あの状況ではああなってしまうのも仕方がないと思う反面、私たちも親子再 統合において、恵津子と同じ苦しみを味わうかもしれないことを心構えし、ヒステリックにならず忍耐強く我が子との関係を再構築していかなければならないのだと感じました。
蝉は地上に出て7日間しか生きられません。もし8日生きた蝉がいたらしあわせでしょうか?と映画は幾度となく私たちに問いかけます。8日生きる蝉は孤独で、辛い思いをするために生きるようなものかもしれません…けれど、8日間の寿命を与えられたなら、孤独も苦労も受け留めて精一杯生きるべきと教えられます。
ぜひこの映画をご覧になり、家族再統合には、どれほどの忍耐と努力と子どもの心理への理解が必要かということをしっかり受け留め、覚悟して八日目を生きていこうではありませんか。