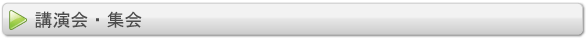【2013.08.12】 親子ネット勉強会レポート 『共同養育社会実現のための勉強会』
親子ネット勉強会レポート
『共同養育社会実現のための勉強会』
親子ネットでは平成25年6月8日に「共同養育社会実現のための勉強会」を開催しました。別居または離婚後の親子が自然に会える社会となるためには、法律の整備と国民の共感、支持が必要です。
今回は、日ごろ、親子ネットの活動を支援していただいています、NPO法人日本リザルツの白須紀子代表に、「国民の意識を変えるために必要なこと」についてご講演をお願いしました。


1.基調講演 (白須紀子代表)
1)日本リザルツについて
リザルツは、政策提言や普及啓発活動(アドボカシー活動)を行っている国際市民グループ(NGO)です。民意の反映された国際援助を実現し、飢餓と貧困の根絶を最優先とする“政治的意思”の確立に向け活動しています。
1985年米国で設立されました。日本リザルツは1989年に発足。イギリス、オーストラリア、カナダ、ドイツ、メキシコ、フランス等のパートナーと共に、各国ODA(政府開発援助)政策等において貧困対策を重視することの必要性を政府に提言しています。
私たちの活動は、草の根の市民から、南アフリカ元大統領ネルソン・マンデラ氏や、米国元国務長官ヒラリー・クリントン氏、経済学者ジェフリー・サックス氏など、世界の著名人に至るまで、幅広い層から支持されています。また、ノーべル平和賞を受賞したグラミン銀行総裁のムハマド・ユヌス氏は、日本リザルツの名誉顧問です。
2)私が日本リザルツの事務局長になった経緯
私がボランティアを始めたのは、1991年に骨髄移植推進財団(骨髄バンク)が設立され、事務局の第一号ボランティアとなったのがきっかけでした。
それまで私は、三食昼寝付きのどこにでもいる普通のおばさんでした。
自由に使える時間もあり、「何かお手伝いできることはありませんか」と骨髄バンクへ行き事務局での電話の対応、宛名書き、街頭でのドナー登録、献血の呼びかけと、ごくごく普通のボランティアさんをしていました。そのおばさんが、震災以来、官邸にもこの復興Tシャツを着て、出入りしています。
骨髄バンクで活動を始めて10年目の2001年1月、娘の大学の先輩が26歳の若さで白血病で亡くなってしまいました。就職も決まりこれからというときでした。この不幸な出来事があり、地道に街頭活動だけをしていても、たくさんの患者さんを救えないと考えるようになりました。
そんな思いから、娘の先輩が亡くなった翌月に開かれた骨髄バンクの公開フォーラムで、勇気を振り絞って手を上げ、震えながら用意した原稿を読み上げました。「30万人ドナー登録早期達成のために、責任官庁である厚生労働省が率先して省内で登録会をして、主体的に取り組む姿勢を示すことが重要ではないでしょうか」と。
驚いたことに、それから10日もしないうちに、本当に、厚生労働省内で献血と併行してドナー登録会をやってくれたのです。 “何か疑問に感じたり不都合があったりしたら、それを伝えることによって世の中が変わるんだ”ということを経験したわけです。
当時、官僚の方に、「私たちの心を動かすことが重要」と言われました。その後、日本リザルツに入りました。
3)政策を大きく動かすために
「私たち一人ひとりに世界を変えていく力がある」このリザルツの理念と私が骨髄バンクで得た教訓が同じものであったということが、現在の活動につながっています。政策を動かすには人の心を動かすこと。専門家しか分からない言葉を使うよりも、誰でも分かる簡単な言葉で訴えることが大切だと思うのです。
日本も、約90年前の関東大震災や今回の東日本大震災では、世界中の国々から支援をしてもらいました。世界中に困った人がいれば、協力するのは当たり前のことではないでしょうか。こんなことを考えながら代表を務めています。
4)親子ネットとの出会い
私と親子ネットとの出会いは、とある会合、まったくジャンルの違う集まりの席で、那須塩原の副市長さんから、ハーグ条約と国内の連れ去り、引き離し問題についてお話を伺ったのが始まりでした。
その後、運営委員の女性2名が日本リザルツのオフィスにいらっしゃいました。初めの印象として、この問題は、離婚して子どもに会わせてもらえなくなってしまったお父さんたちの問題だと思っていたので、女性当事者がいらっしゃることに驚きましたし、詳しい状況を伺うにつけ、日本リザルツとして何かできることがあると考えました。
この問題においては、日本は発展途上国であると感じ、日本の未来を担う子どもたちの健やかな育成のために、また、日本リザルツは政策提言を行うNGOですので、行動指針とも合致しますので、サポートしたいと思うようになりました。
まず手掛けたのは、分かりやすいリーフレット作りでした。今日も来ておりますが、インターンの松倉君が一手に担ってくれました。
皆さんがおっしゃっている、隔週2泊3日、長期休みは1週間程度の、頻繁で定期的な面会交流が、どのように子どもの福祉につながるのか、具体的な数値を盛り込み、親子新法に盛り込むべき内容もできるだけ分かりやすいものにする工夫をしました。また、イラストがかわいらしいので、とっつきやすいものになったと思っています。
このリーフレットを、毎月11日に事務所のある水道橋で行っているつなみ募金でも、大きなNGOイベントや今回の横浜での「アフリカンフェスタ」「アフリカ開発会議」でも、合計1万部を超える部数になるかと思いますが、配りました。全ての衆参両国会議員にも配りました。
また、外務省のハーグ条約担当室長や、重要なポジションにいらっしゃる国会議員にもおつなぎしたり、私が20年のボランティア活動とリザルツの活動の中で築いてきたコネクションをフル活用して、皆様方の思いを国会に届け、願いが実現するために、お手伝いさせていただいています。
親子ネットの運営委員の方々、前代表の神部さんは、つなみ募金に度々来てくださったり、他の方々も、様々なイベント会場でパンフレットを配ったり、事務所でそのセッティングを手伝ってくださったり、できる範囲でご協力くださいます。
5)提言
一つの市民活動が、社会全体に広まり、賛同を得るには、地道な啓蒙活動を根気よく、さまざまな団体と協力して、続けていくことが大切なことです。もう一つ、私が大切にしていることは、せっかく築けた国会議員、官僚、有識者などのサポーターの方々との信頼関係を大切にすることです。
お会いした国会議員には、手書きのFAXや旅先からのハガキを出すとか、1対1でお話した内容は口外しないとか、国会議員の先生、官僚の方々とよい関係性を維持するには、そこの礼儀やマナーを守る必要があります。
皆さんの主張は正しいものです。だからこそ、私たちも支援しようという気持ちになりました。「私たち一人ひとりに世界を変えていく力がある」それを信じて辛抱強く頑張りましょう。運営委員のみならず、皆様が心を一つにして、活動を前に進めていきましょう。「政策を動かすには人の心を動かすこと」です。人の心を動かすには親子ネットとしてどうしていけばよいか、皆さんで話し合い見つけてください。
今まさに、お子さんを連れ去られた直後で、睡眠も食事もできないほど思い悩み、苦しんでいらっしゃる方もいらっしゃることでしょう。どうぞお体にはお気をつけください。しっかり生きて、「親同士が離婚や別居になっても、親と子が自然に会えるあたりまえの社会の実現」を見届けようではありませんか。
2.リーフレット作成について(松倉大樹)
私は、日本リザルツでインターンをしていましたが、事務所で、鈴木さん(親子ネット代表)と白須さんの話をお聞きして、子の連れ去り・引き離しが深刻な問題であることを知りました。私は、大学で人権について勉強をした直後であったため、ハーグ条約や人権問題に関心を持っていました。
学生である私はこの問題に対して、素人でした。しかし、素人であるからこそ、素人でも簡単に理解できる内容のリーフレットを作れたのだと思います。どういう情報を集めれば、より端的に事実を伝え、リーフレットを手にとってくださった方々が、理解して頂けるかに心を砕きました。
国際離婚や、離婚後の親権問題は、当事者でない限り、その深刻さはなかなか理解することが難しい問題です。しかしながら、私自身は、リーフレットの作成を通して、勉強し、皆様と問題を共有することが少しできたと思います。大学で受けた教育を単なる知識として無駄にすることなく、人に役立てる知恵として身につけることができました。本当に得ることが大きかったと実感しています。
3.講演を聞いて
ある心理学者によると、「共感」は、自己を投影して相手も同じことを感じているであろうとする幼児期の段階(いわば自己中心的な共感であり、ヒトや場合によって状況が異なる可能性を考えない)を経て、やがて自分の境遇とは異なる相手の様子を推し量る段階に達するとされています。
この問題は当事者以外はなかなか理解しづらいのかもしれません。しかし、こうして、理解し、共感の輪を広げようとして頂ける当事者以外の仲間が確実に増えています。
政策を動かすには人の心を動かすこと。人に共感すること、人に共感してもらうことの大切さを最認識しました。