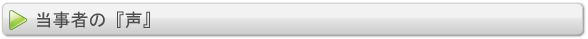『親教育プログラム』がやってきた!(ライター/西牟田靖)
離婚問題を数多く扱う弁護士に話を伺いにいったことがある。そのとき指摘され、虚を突かれたのが、「離婚がこんなに簡単な国はない。紙一枚だけだからね」という言葉だ。離婚を経験し、子どもと離れて暮らすようになるまでは、あまり考えたことがなかったが、言われてみれば確かにそうだ。日本では、離婚届に夫婦がサインし捺印し、届ければそれで終わりなのだ。
諸外国、特に西側の諸外国では離婚やその後のプロセスが日本と異なっている。届けにサインするだけの協議離婚はなく、裁判所の調停手続きが必要であったり、養育費の支払いが義務化されていたり。共同親権制度が整備されていたり。共同養育計画書の提出が義務化されていたり、さらには親教育プログラムというものへの参加が義務づけられていたりする。このように、別れた後も共同で子育てしやすいよう、法制度や行政のバックアップがしっかりしているのだ。
冒頭の指摘をした森公任弁護士が所属する森弁護士事務所のブログには次のような記述がある。「米国では、離婚の最大の被害者は子どもであるという認識が普遍的で、離婚により子どもに精神的ダメージを与えた父母が、その後も、子どもへダメージを与え続けることを防ごうと、親の教育プログラムが、かなりの規模で実施されているようだ」と。
この親の教育プログラムについて、東京国際大学の小田切紀子教授の「離婚家庭の子どもへの支援・後編(http://www.blog.crn.or.jp/report/02/160.html)という論文に内容の一例が記されていた。それによると「①子どもの発達段階の特徴と各発達段階の子どもが離婚に示す反応とそれに対する適切な関わり、②元配偶者と協力して子育てをするための知識とスキルについて、20ページ程のテキストを用い、『離婚と子ども』のビデオ鑑賞、ロールプレイ、グループディスカッションをしながら具体的に学ぶ」とのこと。
どういったものなのか。気になっていたところ、日本でも親教育プログラムが試験的に行われる、ということを耳にした。「離婚と親子の相談室 らぽーる」という団体が、10月25日に親教育プログラムを実施するというのだ。これは厚生労働省の調査研究事業として行われるもので、3月までに3回開催される予定だそうだ。
当日、都内某所の会場を訪れると、30~50代の男女が30人前後集まっていた。5人ずつのテーブルが3卓。加えて、取材などの関係者が1卓。
「共同養育を実現する親であるために」という配布冊子を元に話は進んでいった。内容は先に紹介した小田切教授の論文をほぼ踏襲しているようだ。子どもの病気に際しての自分の振る舞いを思い出したり、「助け無しで2、3歩歩ける」「指を使って物をつまむ」といったことを一般的に子どもがいつできるようになるのか、年齢を記すクイズをしたり、山の形を書いて心理テストをしたりした。
父と母の役割をテーブル別に話し会い、書き出していった。僕のいたテーブルでは、夫婦関係を壊さない方法が主なトピックとして上がっていた。ほかのテーブルでは、日本社会での一般的な男女の行動パターンに即した文言が並んでいて、物のとらえ方の違いを思い知らされた。その後は、子どもへの離婚の告げ方やそれに対しての子どもの受けとめ方を映画の一場面を参考に考えた。そして最後に「共同養育計画合意書」の記入例の紹介もあり、親権・監護権、養育費、支払方法、面会交流の実施方法などが仔細に記されていた。
クイズや心理テスト、グループディスカッションをやっているときは、なんでこんなことをやらされるのか、と正直、首をかしげていた。しかし、受講から4日がたってこれを書いている今、プログラムの意図や効果が少しわかるようになった気がする。夫婦関係が良好だった頃のことや悪くなっていったときのこと、子どもが病気になったときの焦りや、離婚に至るまでの悪夢のような日々…といったことを思い出したり、別れたときの子どもの心理についても想像したりするのだ。
講師役の方たちが「過去と他人は変えられない、しかし未来と自分は変えられる」と話していたが、振り返ると、まさにそうした効果が、徐々にかもしれないが、出てきたのかもしれない。しかし一方、離婚直後の未来が暗闇に閉ざされたような時期にこれを受けたかったという風にも思った。
今後、離婚を検討する夫婦がこのようなプログラムを受けることが全国的に一般的になれば、離婚しても、関係をこじらせず、未来を切り開ける男女が増えるはずだ。僕は間に合わなかったが、今後、日本に定着することを切に望んでいる。