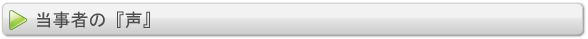女性だって引き離される(3)「いつかは会える日が来るから…」 nana
私は平成19年に引き離しを受け、苦しんでいる母親です。元夫に家を追い出され、子どもに会えなくなりました。一日中子どもの事を思い続けて、食事も睡眠も摂れなくなり、苦しみ悩む日々を送りました。
何が起きているのか、どうしたらいいのか全く分からないまま、調停を始めました。裁判所なら、夫婦が別居・離婚したからといって、親子が会えなくなることを、どうにかしてくれるだろうと信じて…。
しかし、実際はそうではありません。結局は子どもの取り合いで、お互いを罵り合うばかりでした。元夫は、子どもを私に会わせないために、子どもを囲い始めました。調停での事、書類をすべて子どもに伝え、私の悪口を子どもに言い続けました。PASが進行し、私が会いにいくと、子どもが逃げ出すまでになりました。子ども達は私に「会いたくない」と言うようになり、その結果、親権は取れず、月1回の面会交流を約束して離婚しました。でも、子どもが会いたくないとの理由で、元夫は子どもと私とを完全に引き離しました。3年間、子どもとの交流が出来ない辛い日々が続きましたが、毎月子ども宛にハガキを送っていました。
でも、突然状況が変わりました。それは、元夫が変わったからです。囲い込みをやめて、お母さんに会ってもいいと子どもに伝えたのです。子どもが成長し、母に会いたいと言えるようになった事もあるでしょう。長男が高校2年生の夏でした。その後、長男と会うたび、急速に親子の関係は修復出来ました。今高校3年生の長男は、彼女との事を相談してきたり、家での不満を言ってきたりして、離れて暮らしているからこそ話せると思うのですが、頼れる場所が私になっている事を嬉しく思います。今ではバイト帰りに週2回くらいは私の家に寄って、いろいろ話をしてくれます。年末からお正月にかけて、長男が入院していた為、仕事帰りに毎日病院に通って、母親らしい事をしてあげる事もできました。会えなかった3年間は戻ってこないけれど、今、離れて暮らしていても出来ることを子ども達にしてあげるために、私は日々頑張っています。金銭的にも、精神的にも、頼ってきた時に応えられる強い母でありたい。子どもから、「お母さんは、会うと泣くから嫌だ」と言われたから、私は会えなくなってから、もう絶対子どもの前では泣かないと誓い、頼ってきたら何でも受け止められる母になりたいと自分を奮い立たせ、仕事にも、生活にも、自分の全てに自信をもてるように頑張ってきました。
そして、PASが一番ひどかった次男が、中学2年生の3月に、突然会いに来ました。ジュニア野球の日本代表で台湾遠征に行くから、お金を援助して欲しいとの事で、母として頼られたのです。私は離婚で辛い思いをさせてしまったことを謝り、これから離れていても親子には変わりはなく、出来る限りのことをしてあげたい。ずっとお母さんは子ども達のことを死ぬまで愛していることを、精一杯泣かずに真剣に伝えました。そして次男に援助をし、台湾遠征に行かせてあげました。
今、中学3年生になった次男が、「お母さんに会いたくないと言っていたけれど、そう言うしかなかったんだよ。一度もお母さんに会いたくないなんて思ったことないよ。どれだけお母さんがいなくなって、大変で、家が変わったと思う?辛かったよ。だから、12歳と9歳の弟達も、お母さんに会いたくないと言っているけど、会いたいに決まってる。今は無理なだけだよ。」と言ってくれた時には胸がいっぱいになりました。最近一番嬉しかったのは、高校で使うグローブを入学祝いでプレゼントしたら、そのグローブに特注で「親に感謝」と文字を入れ、ガールフレンドを連れて見せに来てくれたことです。引き離された時には「くそばばあ。会いに来てんじゃねぇよ!」と私を一番罵っていた次男でした。長男から聞いた話ですが、引き離しにあってすぐの5年生だった頃、一番泣いて私に会いたがっていたのは、次男だったそうです。
そして、次に会えたのは、四男でした。5歳だったのに今はもう9歳。甘えん坊で私にべったりだったのに、引き離された頃には会いにいくと泣きながら逃げ出していました。それが、去年のクリスマスに手作りケーキとプレゼントを渡しに行った時、長男が四男を連れて出てきてくれました。四男はどうしていいか分からないのか、私が「おいで」と声をかけても、車の陰から出て来られませんでした。「いいよ。そこで聞いて。今日はお母さんに会いにきてくれてありがとう。それだけで嬉しいし、頑張ったね。お兄ちゃん、ケーキ持てないから、お願いだから取りに出てきて」と声をかけると、私の目の前まで可愛い顔を出して、ケーキを受け取ってくれました。長男が「お母さんと握手だけでもしろよ」と言ってくれましたが、出来なかったので、「プレゼントもらったら、ありがとうは言わないとダメだよね」と私が言うと「ありがとう!」と声を聞くことが出来ました。目の前にいる我が子を抱きしめたいのをグッと我慢してその日は別れました。
三男は6年生。今はまだ難しい状態ですが、誕生日のケーキを作ってあげたら、「『ありがとう』とお母さんに言ってねと言っている」と元夫からケーキのろうそくを笑顔で吹き消す写メールが送られてきました。
子どもはお父さんもお母さんも大好きです。今は、子どもの為に元夫となるべくよい関係を保つように努力しています。そして私は出来る限り協力して子育てしていきたいと話をしています。
会えていなくても、諦めず元気でいること。会いに来てくれた時に頼れる母でいたいと頑張ってきたから子どもに会えていると思っています。
ご案内-親子ネットに相談ください!
親子ネットでは連れ去りにあった当事者(被害者)のために、毎月、定例会を開催し親身に相談にのっています。一人で悩まずに気軽に相談してください。親子ネットは10年以上の歴史を持つボランティア・ベースの会員数約500名の国内最大の当事者団体です。
お問い合わせは、こちらのページよりお願いします。