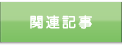2017年03月20日 ニューズウィーク 『DV防止法のせいで、わが子に会えず苦しむ父親もいる』
DV防止法のせいで、わが子に会えず苦しむ父親もいる
<父親たちの本音をすくい上げるノンフィクション『わが子に会えない』。気になるのは、実際には暴力をふるっていないのに「DV夫」のレッテルを貼られ、子どもに会えなくなる人もいるということだ>
『わが子に会えない――離婚後に漂流する父親たち』(西牟田靖著、PHP研究所)は、ある日突然、子どもと会えなくなってしまった父親たちの本音をすくい上げたノンフィクション――とだけ聞いてもピンとこないかもしれないが、冒頭に登場する「ある事件」についての記述を読めば、どういうことなのか推測できるはずだ。
2013年のXマス2日前、都内の小学校の校庭で男性とその息子が発火するという事件があった。消し止められたが助からず、ふたりとも命を落としてしまった。男性はマスコミに勤務する40代。野球の練習をしていた息子を校庭の隅へと連れ出した後、自らに火をつけた。妻子と別居中だった男性は、子どもに会うことを制限されており、しばしば妻子の家や学校に現れることがあったという。(2ページ「プロローグ」より)
たしかに、そんな報道があった。痛ましい事件だったが、その背後には、子どもに会いたくても会わせてもらえない父親の苦悩があったのだ。そして忘れるべきでないのは、上記の父親のように子どもとの面会を制限され、精神的に追い詰められていく人は現実に多いのだろうということだ。なにしろ、年間20万組以上が離婚しているのだから。
なお、本書に説得力を与えている要因がある。著者自身が、上記の事件のすぐあとに当事者になってしまったということだ。
翌年の春、妻が3歳の子どもを連れて出ていき、夫婦関係が破綻した。離婚届を受理したという通知が役所から届いたとき、一時的に記憶がなくなり、自転車をなくすほどであった。愛してやまない当時3歳の娘に会えなくなったことが、なんといってもショックだった。自分の両手をもがれてしまったような喪失感がしばらく続き、いつふらっと線路に飛び込んでもおかしくはなかった。生きている実感がまるで湧かず、体重は10キロほど落ちた。(2ページ「プロローグ」より)
そこで著者は、わらにもすがる思いで、同じように子どもと会えなくなった親たちが体験を共有する交流会に参加する。つまりそのような経緯を経て、本書は必然的に生まれたのである。
気になったことがある。身に覚えのないDV(ドメスティック・バイオレンス)を主張され、子どもに会わせてもらえず、苦しんでいる人が多いという話だ。
「数えていたわけではないが、全体の半分ぐらいはあっただろうか」と著者は記しているが、たしかに本書で紹介されている人の多くが「DV夫」としてのレッテルを貼られている(もちろん女性がその立場に立たされているケースもあるのだろうが、男性当事者の数が圧倒的であることから、本書もそちらに焦点を当てている)。
【参考記事】児童相談所=悪なのか? 知られざる一時保護所の実態
背後にあるのは、2001年にDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)が制定されたことだ。「配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律」[内閣府男女共同参画局HP]というもの。具体的には、次のように行使されるのだそうだ。
――被害者は配偶者暴力相談支援センターや警察などへ出向き、DV被害について相談する。行政は被害者の申し立てを受けて被害者の居所を秘匿する。希望者は配偶者(加害者)の暴力から逃れるためにシェルター(ほぼ女性のみが対象の一次避難施設)などに避難。地方裁判所が認めれば、加害者に対し保護命令に含まれる接近禁止令や(世帯が居住する家からの)退去命令が発令される――。(5ページ「プロローグ」より)
子どもに会えなくなる状況を生み出す原因がここにある。離婚して親権を得たいパートナーが、実際にはないDV被害を訴えることで保護を望む。行政はそれに応える。結果として、加害者扱いされた側は子どもに会う機会を失う。もちろん世の中には実際にDVに苦しんでいる人も大勢いるだろう。しかし一方には、こうした経緯により「DV夫」にされてしまう人も少なくないということ。(被害者たる)パートナーを守るための制度が、本来の目的とは違う形で使われているわけだ。
「『暴力を受けた』と言った者勝ちなんです。証拠だとはとても言えないあやふやな主張がひとつひとつ積み重ねられ、DV被害者としての肩書きというか実績がどんどん加わっていくんです。裁判でDVの認定が却下されたというのに、行政や警察は、妻の言うことすべてを鵜呑みにして、妻子の住所を私に秘匿したまま。私が調べて欲しいと言っているのに、警察が捜査をしたり話を聞きに来たりしたことは一度もありません。本当に私が暴力を振るったんなら刑事事件として立件すればいいんですよ!」
40代の会社経営者、長谷川圭佑さん。穏やかで優しそうな顔をそのときばかりは引きつらせた。(59ページより)
このように、「暴力を受けた」という一方的な主張によって追い詰められる人もいることを、本書は証明している。どうしようもできずに泣き寝入りする人がいれば、納得できないからと徹底的に争う人もいる。対抗策は人それぞれだが、一般的な感覚からすると首をかしげざるを得ないようなことが現実に起きていることだけは間違いないようだ。
ちなみに本書に登場する父親たちの大多数は、裁判所や弁護士の世話になった結果、耳を疑うようなつらい体験をしてきたのだという。裁判所に悪意があるわけではなく、それどころか彼らには善意があり、専門知識を持ったスペシャリストであるはずだ。しかし官僚組織である裁判所においては、組織として回していくことが、公平な紛争解決よりも、組織防衛上、なにより重視されるということだ。
【参考記事】家事をやらない日本の高齢男性を襲う熟年離婚の悲劇
裁判官1人あたり100件以上の訴訟案件を抱えており、さらに毎日数件のペースで案件が増えていくと聞けば、致し方ない話ではあるのかもしれない。でも、だから父親たちは我慢を強いられなければならないのだろうか? 幸いなことに、そういうわけでもなさそうだ。日本でも面会交流の拡大や共同親権制度への変更に向け、国や行政が重い腰をあげるようになってきたというのである。これはアメリカの30~40年前の動きに近いそうだが、ともあれ期待したいところである。
これまで”離婚=親子の別れ”という考えが強く、そのために別れて暮らす子どもと別居親が会うことが困難を極めた。しかし、世の中は変わりつつある。(中略)争ってでも会おうとしている親が確実に増えてきたのだ。そうした声を受けてのことなのか。子どもと離婚に関して記した日本の民法766条が2012年に変更となった。”面会交流と養育費の分担”について追記されたのだ。
2016年10月に法務省は、養育費に関する法律解説や夫婦間で作成する合意書のひな型を掲載したパンフレットを作成し、全国の市区町村の窓口で、離婚届の用紙を交付した際に配ったり、法務省ウエブサイトで公開し始めている。また、裁判所にしても面会の”相場”をゆるめつつある。(317ページより)
戦後、日本の家族の形が変わるなかで、女性の社会進出が進み、DV防止法ができるなど、女性の権利が守られるようになった。それ自体はとてもよい傾向だ。しかし今後は、父親たちや男性たちの権利も、もっと認知されるべきだと著者は主張する。つまり、そうした権利を求める動きのひとつが、父親が子どもに会ったり共同親権を求めたりする運動だということ。
――男だって子どもと存分にふれ合いたいし、育てたい。親として子どもと一緒に生活することで、生きて行くことの喜びを感じたり、親として成長していきたい――。(317ページより)
著者のこの言葉にこそ、子どもに会えない父親たちの本音が集約されているのだろう。
[筆者]
印南敦史
1962年生まれ。東京都出身。作家、書評家。広告代理店勤務時代にライターとして活動開始。現在は他に、「ライフハッカー[日本版]」「WANI BOOKOUT」などで連載を持つほか、「ダヴィンチ」「THE 21」などにも寄稿。新刊『世界一やさしい読書習慣定着メソッド』(大和書房)をはじめ、『遅読家のための読書術――情報洪水でも疲れない「フロー・リーディング」の習慣』(ダイヤモンド社)など著作多数。