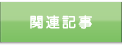2017年02月08日 BLOGOS 『“DV冤罪も…”我が子に会えない父親たちの苦しみ』
“DV冤罪も…”我が子に会えない父親たちの苦しみ
DV認定はされずも、親権は母親に
人口動態統計によると、日本では、年間20万件以上、つまり夫婦の3組に1組が離婚している。人口1000人あたりの離婚率は1.77(2016年)だ。そんな中、子どもと会えない親たちがいる。
先日も、別居中の夫婦が、9歳の長女の親権をめぐって争った裁判の判決があった。千葉家裁松戸支部(庄司芳男裁判官)は2016年3月、長女と別居しながらも、「年間100日、母親が子どもと面会できるようにする」と提案する父親に親権を認めていた。しかし、17年1月26日、東京高裁(菊池洋一裁判長)は、子どもと同居する母親を親権者とする判決を下した。傍聴席には、自らも子どもと会えない時期があったノンフィクション作家の西牟田靖さんが座っていた。『わが子に会えない 離婚後に漂流する父親たち』(PHP研究所)を上梓したばかりだ。
東京高裁での親権争いは、母親に親権を認めた結果になった。判決によると、母親は10年に長女を連れて実家に帰った。別居する父親は何度か長女と面会していたが、夫婦関係が悪化するにつれて、面会交流が難しくなっていた。この裁判では、「年間100日」という、欧米では標準的な面会交流の日数を提案している父親に親権を認める千葉家裁の判決を東京高裁がどう判断するのかが焦点だった。
いわゆる、フレンドリー・ペアレント・ルール(友好的親条項)というものがある。離婚後に子どもの親権を決める際、別居の親と子どもの面会交流に協力的か、別居の親を子どもに肯定的に伝えることができるか、など親権者として適正かどうかを判断する。千葉家裁はこのルールにそった内容だった。しかし、日本でこのルールを適用したのは異例だったと言える。
一方、東京高裁は継続性の原則を重視し、長女と同居する母親に親権を認めた。つまり、生活環境が安定していれば、現状維持となる。異例だった千葉家裁判決とは違い、これまでの判例通りの判断をした。別居時に、一方が子どもを連れて出ていくことを“連れ去り”と言われることがあるが、継続性の原則は、どんな形であれ、一緒に住んでいる親を親権者として認めるものだ。
私は判決言い渡しを傍聴していたが、西牟田さんも傍聴席にいた。その後、夫と妻それぞれの会見が司法記者クラブであったが、2人とも会見に参加した。母親に親権を認めた点に「結局、継続性の原則が勝つのか…」と思ったようだ。また、夫側の会見では、妻側が“夫はドメスティック・バイオレンス(DV)の加害者”と主張し、それを前提に署名活動が行われていた点に、弁護団は憤慨していた。裁判では証拠がなく、DVは認定されなかった。
『わが子に会えない』でも、妻側にDVを主張されて、警察に逮捕されるケースまで描かれている。西牟田さんはDV冤罪について「人はそれなりの正義を持っている。強固であるほど意見や立場の異なる人たちに関する許容度は減るのではないか」と感想を持ったようだ。
この裁判では、夫側が判決を不服として上告した。最高裁が受理すれば、裁判は続く。私としては、夫婦の関係崩壊は仕方がないとしても、実際に子どもへの危険がない限り、親子ができるだけ自由に面会できる権利や環境整備をしてほしい、と願うばかりだ。
普通の生活をしている常識人でも”被害”に遭う
西牟田さんが、離婚後に子どもに会えない父親をテーマに執筆しようと思ったのは当事者だったためだ。離婚後、子どもと会えない時期があった。当事者の団体を知人を通じて知り、交流会に出かけ、問題意識を持つようになった。
「交流会に参加する以前は必死だった。家族の崩壊を食い止めないといけないと思っていたし、こうなったのは自分が悪いからだ、と責めることもあった。精神的に参っていたので、門を叩いた」
子どもに会えない苦しみは自分だけなのか。そう思っていると、同じく苦しんでいる人がいるとわかった。知人の報道ディレクターがFacebookで書き込んでいたからだ。彼の話を取材し、雑誌に掲載しようと思ったが、その矢先、彼は自殺した。理由は単純なものではないだろうが、
「家族のことが一番の問題だった、と聞いた。それで余計に深刻な問題なんだ」
と思った。
『わが子に会えない』では、18人の当事者が出てくる。夫婦の関係が崩壊する理由もさまざま。浮気によるもの、妻の精神的な不安定さ、結婚に反対していた義父母による妻子の囲い込み、妻からのDV、宗教が原因となるもの……。インタビュー集のため、どのパターンをどう解決するといった手立ては書かれていない。また、父親が言っていることが事実かどうかわからない。一方的ではあっても、会えない辛さを訴える当事者が目に前にいることはたしかだ。
西牟田さんは現在、子どもとの面会ができている。しかし、会えるようになるまで離婚してから1年3ヶ月がかかった。今年も2回、元妻と子どもと3人で会うことができている。自身も同じ苦しみをしたという意味で、取材や執筆は辛くなったのだろうか。
「僕自身が当事者だが、裁判も調停もしてないので、どのケースにも似ていない。ただ、『僕の見た「大日本帝国」』(KADOKAWA)、『誰も国境を知らない』(朝日新聞出版)などの歴史ノンフィクションでは、右でも左でもなく、中立というのが売りで、途中でエクスキューズを入れていた。しかし、今回は、彼らの声を薄めずに、そのまま書くようにした。そうじゃないと、(突然子どもと会えなくなる)“災害”のようなものに遭っていることが伝わらない」
今回は、子どもに会えない父親側に立った本だが、どんな点に気をつけて書いたのか。
「バックグラウンドがバラバラな、あらゆる男の人が“被害”に遭っていることをわかってもらうために、人となりも紹介した。父親が暴力をしているのでは?と見られがち。しかし、いかに普通の生活をしている常識人であることを踏まえつつ、“連れ去り”被害を書くことにした。そのため、地下鉄サリン事件の被害者のインタビューをまとめた、村上春樹の『アンダーグラウンド』(講談社)や、原発事故被災者の声を丹念に聞き取った、スベトラーナ・アレクシエービッチの『チェルノブイリの祈り』(岩波書店)を意識した。もちろん、嘘をついているかどうかはわからない。しかし、それを含めて伝えようと。今回はイタコになろうと思った」
親子断絶防止法は共同親権の足がかりになるか?
この問題をどう解決すべきだろうか。
「別れた後の処理が、ベルトコンベアのように機械的になっている。司法が関わると、なおさら大変だ。欧米では、100日面会が相場だ。諸外国のように、共同親権が認められればいい。現状では、『共同親権を実現せよ』と、声高に言っている政治家はいないが、前段階として、親子断絶防止法の制定を願っている」
親子断切防止法案は、子どもには両親の愛情が必要という前提に立ち、夫婦が離婚をしても、頻繁かつ継続的な親子交流ができ、また子どもを同意なく連れ去ることを禁止するものだ。そして、共同親権も導入すべき、と付帯決議で提案もする予定になっている。
「親子断絶防止法は共同親権への足がかりになればいい。もちろん、夫が“連れ去る”というケースも知っている。そのため、別れるのは手順が必要です。現状では義務ではないため、制度化するべき」
ただ、慎重な意見も多く、具体的な政治日程には上がっていない。DVは証拠に基づく、とされているが、証拠を保全する余裕がない場合もある。妻への暴力がある場合は、子どもへの暴力の可能性も高い。これを禁止されると、子どもを守れない。一方で、加害行為がないのに、DV冤罪を主張される場合がある。『わが子に会えない』では逮捕されたケースも掲載されている。議論が成熟はしていない。
もちろん、“連れ去り”をするのは母親だけではない。
「父親が“連れ去る”というというケースも取材したことがある。ただ、今回、父親に絞ったのは、親権は母親が優先されている現状があり、それを顕在化したかった。それに、自分が男で共感がしやすかったから」
最後に一言。
「結婚したときと子どもが生まれたときでは状況が変化する。結婚は、相手の常識とこちらの常識とのすり合わせ。子どもが生まれればなおさらだ。取り上げた人に対して感情移入はしている。僕の場合は、トラブルにあっても、別れても、復縁の目がなくても、家族だと思っている。ただ、この本を読むと、結婚に希望を見出す人が減るのかもしれない。でも、こういう問題がなくならないといけない」