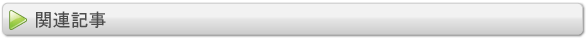2016年05月10日 政治山 『連れ去りから6年、親権を勝ち取った男性から見た離婚裁判』
連れ去りから6年、親権を勝ち取った男性から見た離婚裁判
子を持つ夫婦が離婚する際、日本では一方の親だけが親権を持つ「単独親権」が民法で規定されています。欧米で一般的な「共同親権」は認められていません。離婚裁判では、たとえ妻が子どもを連れ去る形で別居した場合でも、母親側に親権が認められるケースが多く、わが子との突然の別離に苦しむ男性は少なくありません。
画期的な判決「母親でなく父親に親権」
そんな旧態依然とした家族制度を見直し、父親である夫に親権を与える画期的な判決が3月29日、千葉家裁松戸支部(庄司芳男裁判官)で言い渡されました。
判決によると、夫婦の間で2007年に長女が生まれたものの、妻は2010年5月6日、夫に無断で長女を連れ去り実家に戻りました。妻はその年の秋を最後に面会を拒み、夫は5年半にわたって長女と一度も会うことができません。
夫は年間100日程度の面会交流計画を提示
訴訟で、妻は離婚を求めるとともに、別居後長女と同居してきたことを踏まえ「慣れ親しんだ環境から引き離すのは長女の福祉に反する」と主張。夫と長女の面会交流は「月1回」と提案しました。
これに対し、夫は隔週末に48時間の面会のほか、連休や誕生日についても隔年で面会を認めるなど、妻と長女の面会交流計画を「年間100日程度」提示していました。
「寛容性の原則を初めて採用した判決」
判決では、夫婦で長女の成長を支えるためにはより多くの面会日数を提案した夫の方が親権者にふさわしいと判断し、妻に長女を引き渡すよう命じました。判決後、記者会見した男性側代理人の上野晃弁護士は、「(子どもを見ている親が、他方の親との面会交流に協力的かどうかを親権者の適格性判断の基準とする)寛容性の原則(フレンドリー・ペアレント・ルール)を明確に採用した、おそらく初めての画期的な判決」と語りました。
男性は突然の別離から面会交流が一切叶わず、調停と裁判を繰り返してきました。やっと長女に再会できるという喜びも束の間、妻は判決を不服として控訴し、再会はさらに遠のくこととなりました。新たな判例を背景に控訴審に臨む男性から、法曹界に対する疑問や判決に対する思いを政治山に寄稿していただきましたので、全文を下記に掲載します。
■連れ去り親が親権者として相応しくないと判断した点でも画期的
私のこの判決は、寛容性の原則を採用しただけでなく、子どもの連れ去りと親子の引き離しをした親が親権者として相応しくないと判断した点でも画期的です。しかし、この判決内容は決して突飛なものではありません。むしろ、法に基づき適切に判断されたものです。
■法務大臣「無理して子を移動させて、後は継続…あってはいけない」
平成24年4月、民法766条が改正され、親権・監護権の決定時に「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされました。この改正に伴い、法務大臣が国会で以下のように答えています。
「面会交流に積極的な親が監護権決定に有利に働くように、あるいは面会交流を正当な理由なく破ったら監護権者の変更の重要な要素になり得る」
「別れる場合に、子の監護者を決める。そのときに、相手に対してどちらの方がより寛容であるか。片方が、いや、月1回会わせます、もう片方は、いやいや、月に2回は会わせます、それなら、その月2回会わせる方を監護者に決めよう、そういうルールといいますか、裁判所のやり方(は)重要な指摘」
「合意ができる前にあえて無理して子を移動させてそして自分の管理下に置けば、後は継続性の原則で守られるという、そういうことはやっぱりあってはいけない」
この法務大臣答弁を周知徹底するため最高裁から全裁判所に対し、少なくとも3回(平成23年8月3日、平成24年3月29日、平成26年3月17日)書簡が出されています。
■最高裁長官「ハーグ条約…国際社会の潮流も見据えて検討を」
さらに、平成26年4月1日の就任時に最高裁判所長官は「裁判所にとってハーグ条約関連法にあるように、家庭内の出来事が視野に入ってくることも普通に見られるようになっている。このような状況に対応し、司法の機能を充実、強化していくため、国内の実情はもとより国際社会の潮流も見据えて検討を深め、国民の期待と信頼に応え得るよう不断に努力を重ねていくことが求められている」旨の発言をされています。
■多くの裁判官は民法改正を徹底的に無視
以上から明らかですが、今回の判決は、民法766条の改正を踏まえれば当然の判断です。逆に言えば、多くの裁判官は、民法改正後、本判決が出るまでの4年間、最高裁からの再三の要請にもかかわらず、この民法改正を徹底的に無視してきたということです。そして、裁判官は、子どもを奪われた親の親権を、「親子が引き離されている」ことを理由に奪い続けてきました。これがいわゆる「継続性の原則」ですが、法律上どこにも書いていません。
このような絶望的な状況に直面し、数多くの子ども想いの親が自殺に追い込まれました。心中に及んだケースもあります。裁判官が民法改正を踏まえて判決を下していれば、少なくとも、この方たちは亡くならずに済みました。
また、一方の親から引き離された子どもがもう一方の親らにより虐待され殺される痛ましい事件もしばしば起きています。今回の判決が命じているように、年間100日の面会交流が行われていたら、このような虐待死は起こらなかったはずです。これらのことを思うと、悔しくて仕方がありません。
■最後に
今回の判決は、もっと早くに出ていなければならないものでした。既に亡くなられた親と、その子どもたちとの、本来あったはずの幸せな生活は残念ながら決して実現しません。
自殺や虐待死に至らないまでも、多くの親子が、今の裁判所の運用に苦しめられています。私も、娘が連れ去られてから約6年間、一日も心休まる日はありません。娘が戻って来る日までこの苦しみは続きます。2歳で連れ去られた娘は約6年にわたり父親と全く会えずにいます。娘は、父親に捨てられたと思っているかもしれません。何ら罪のない娘にこんな状態を強いる仕組みが「子の利益」に適うとは私には到底思えません。
このような辛い思いをする親子は2度と出てきてほしくありません。我々親子の犠牲を無駄にしないでほしいと思います。
今回の私の判決のように、民法766条の改正趣旨に従い適切な判決が下されるだけで、多くの親子が救われます。また、これから起こりうる子どもの連れ去りや引き離しも未然に防げます。将来にわたり多くの命を救うことにもなります。ぜひ、そのように裁判所の運用が一刻も早く変わることを願います。
同時に、社会の「常識」も変わっていってほしいと思います。夫婦の別れが親子の別れになってはいけません。離婚は仕方がない場合でも、できる限り、そのしわ寄せを子どもにいかせない努力が必要なのだと思います。ぜひ、私のこの判決を「子の利益」とは何なのかを考える契機にしていただければと思います。