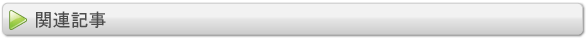2013年01月24日 朝日新聞 『(いま子どもたちは)親が離婚した…:1 親への恋しさ、我慢した』
(いま子どもたちは)親が離婚した…:1 親への恋しさ、我慢した
No.450
「お父さんが出ていく日、泣かないようにして下を向いて見送りました。その後、玄関に座り込んでずっと泣いていました。不仲なのはわかっていたけれど、子どもとの関係まで壊さなくていいと思いました」(小学6年女子)
「母が毎日のように離婚した父の悪口を言うのがつらい」(中学1年女子)
「母の新しい彼氏を受け入れられない。誰にも相談できず、一人で考え込んでしまう」(高校2年女子)
親の離婚や再婚を経験した子どもたちを支援するNPO法人Wink(東京都新宿区)のウェブサイトにある掲示板には、子どもらの悲痛な思いが、途切れることなくつづられていく。
「がんばりすぎちゃダメ。悩みを話せる友だちはいますか」
「本音を言えない気持ち、わかります。言ったら家族関係が壊れちゃうしね」
Winkの新川明日菜理事長(24)は、一つひとつ丁寧に返信する。「親の離婚を経験した子どもの大半は、親友にはもちろん、同居する家族にも本当の気持ちを隠している」と話す。
東京都出身の新川さんも、離婚家庭で育った。最初の離婚は0歳の時。その後、母が再婚、離婚、事実婚を繰り返し、成人するまでの間に3人の「父」と暮らした。「母は子どもより恋愛が大切な人。父だった人も、みんな去っていった。自分の家庭はふつうじゃないと思い、自己肯定感が低かった」
*
13歳のとき、実父が唐突に養育費を支払うようになった。記憶にない実父に興味はなかったが、誕生日の月に支払いを上乗せしてくれたとき、「会ってみたい」と心が動いた。
東京都台東区のJR上野駅で待ち合わせ、2人で食事をした。再婚していた実父は、新川さんが赤ちゃんだったころの写真をボロボロの状態で持っていた。離婚を謝り、「こんなにいい子に育ててくれて感謝している」と母への思いを口にした。
「自分を愛してくれる人がいる」。新鮮で温かい発見だった。大嫌いだった母との関係も、少しずつ改善した。
自分と同じように悩む子どもたちの声を聞いてあげたい――。2010年、Winkの活動の一環として、子どもたちに同じ境遇で育った大学生らを家庭教師として派遣する事業を始めた。離婚や1人親家庭の親への支援はあっても、子どもの支援は少ない。そんな現状を変えたかった。
現在、家庭教師は35人。その一人、都内の大学1年加藤涼也さん(19)は、訪問先の小学4年の男の子にかつての自分を重ねている。昨年のクリスマスイブ。「ケーキを買ってやる」と言うと、「そんなのいらない!」と断られた。やさしさに慣れないため、わがままを言えず、甘え方がわからない男の子。そんな姿を見るのがつらかった。
*
かつて加藤さんも、遠慮しがちで、冷めた目で周囲を見る子どもだった。ともに20歳で加藤さんを授かった両親は、3年後に離婚し、母方の祖父母に育てられた。母は仕事に忙しく、2週間に1回帰ってくる程度。父とは小学1年のときに1度だけ会ったきりで、どこで何をしているのかわからない。
泣いた記憶は1回だけだ。小2のとき、家で偶然、両親の結婚記念につくられたオルゴールを見つけた。両親の名前が刻まれた箱をパカッと開けると、流れてきた曲は、中山美穂とWANDSの「世界中の誰よりきっと」。互いを思いやる気持ちを歌い上げた愛の歌に、涙が出て止まらなくなった。
「我慢してるつもりはなかったんですけど……。やっぱりしんどかったのかな」。祖父母には、たくさんの愛情を注いでもらった。それでも、「両親が恋しい。友だちと自分の間に距離を感じることが多かった」。
今夏、20歳になる。母に父のことをきちんと聞いて、会いに行くつもりだ。20歳で父親になった父に「同じ年になったぞって言いたい」。好きだったと聞かされているたばこを一緒に吸って、「どこか似ているところを見つけられれば最高です」。
◇
置き去りにされがちな離婚家庭の子どもたちを取材した。(古田真梨子)
◆離婚する家庭の子ども、年に20万人 強い偏見、心に負担も
厚生労働省の人口動態調査では、2011年に親が離婚した未成年の子どもは23万5200人。90年代半ばから20万人台が続き、最多だった02年は29万9525人。その後は減少傾向だが、早稲田大学の棚村政行教授(家族法)は「婚姻数も減っている。離婚が減っているという実感はない」と話す。
日本では、子どもがいても、夫婦間の合意だけで離婚することができる。離婚後の親子関係について十分な話し合いがなされず、子どもが片方の親と断絶するケースも多い。棚村教授は「親同士のいさかいと、子どもの利益を分けて考えなければいけない」と指摘する。
昨年4月1日、離婚届に「面会交流」と「養育費」について取り決めをしたか否かを尋ねる欄が新設された。記入しなくても離婚はできるが、法務省は「夫婦に協議する機会を与えられれば」と親たちの意識改革に期待を寄せる。
東京国際大学の小田切紀子教授(臨床心理学)は「日本では離婚家庭への偏見が強く、『うちは普通じゃない』と心を閉ざす子も多い。親は子の気持ちに最大限の配慮を」と訴える。
小田切教授は、米オレゴン州で離婚家庭の支援を研究している。同州では、離婚する親は、子どもに与える影響を学ぶプログラムを受講しなくてはならないという。「子どもの健全な成長が共通の願いであることを確認することで、子どもの心の負担が減る」と話している。
小田切教授は、米オレゴン州で離婚家庭の支援を研究している。同州では、離婚する親は、子どもに与える影響を学ぶプログラムを受講しなくてはならないという。「子どもの健全な成長が共通の願いであることを確認することで、子どもの心の負担が減る」と話している。