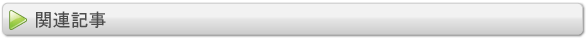2012年06月26日 日経ビジネスオンライン 『日本人による“米国人拉致”問題の行方』
日本人による“米国人拉致”問題の行方
条約の批准だけで問題が解決するのか?
“Abduct”という動詞をご存じだろうか。北朝鮮による日本人拉致問題について報じるとき、英語メディアが使う言葉である。Oxford English Dictionary の定義には“To take (a person) away by force or deception, or without the consent of his or her legal guardian; to kidnap”(誰かを無理やりもしくは騙して、または法的保護者の合意なしに連れ去る。誘拐する)とある。
ただ、日本絡みでこの単語がよく使われるケースがもう1つある。国際結婚が破綻した夫婦間で、一方の親が子供を母国に連れ帰るトラブルだ。具体的には、米国人など外国人と離婚した日本人女性が、相手の合意なしに子供を連れて日本に帰国してしまうケースが多い。
この問題が特に注目されるきっかけになったのは、2009年9月にテネシー州の男性が来日し、元妻と一緒に日本で暮らしていた子供を強引に米国に連れ帰ろうとして、福岡県警に未成年者略取容疑で逮捕された事件だ。米国のCBSニュースのレポーターは事件発生直後、“Mr. X’s ex-wife Y abducted their children this summer and took them to Japan”(X氏の元妻であるYは今年の夏、夫妻の子供たちを拉致し、日本に連れ帰った。報道時はX,Yともに実名)と報じていた。テネシー州の裁判所による決定を無視し、子供たちを日本に連れ帰った妻の行動こそ“拉致”と表現したのだ。
「親による拉致は、国際社会では犯罪」
米議会下院は2010年9月に、この問題を巡る日本の対応を非難する決議を採択した。そのとき演説したバージニア州選出のジェームズ・モーラン議員は“They (Japanese officials) are directly complicit in these abductions.(日本の当局者はこれらの拉致事件に直接加担している)”と訴えた。英語ネイティブに聞くと、非常に強い批判の表現のようだ。「こうした行為を誘拐とみなす米国をはじめ、国際的には犯罪とされる親による拉致を、日本は犯罪と認識していない」とも語った。
批判の裏には、主要先進国で「ハーグ条約」を批准していないのは日本だけ、という事情がある。ハーグ条約は1980年につくられた国際条約で、正式名称は“Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction(国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約)”。ここではabductionの訳語に「奪取」があてられているが、奪取は「敵塁を奪取」などスポーツでも使われることもあり、訳語は比較的穏当な印象を受ける。「拉致」「誘拐」「略取」などでは語感がきつすぎるという判断があったのだろうか。
ハーグ条約のもとでは、親による国外への不正な連れ去りがあった場合、もとの居住国に子供を返還することが基本ルールだ。世界80カ国以上がこの条約を批准しているのに、日本は批准していない。だから日本に連れ去られた子供が帰って来ない、というのが米議会や子を連れ去られた米国人の親の言い分だ。高まる批判を受け、日本政府は2012年3月9日、条約締結に必要な裁判手続きなどを盛り込んだ、ハーグ条約実施法案を決定した。
国際的な家族のトラブルを、国際的ルールに基づいて解決しましょう、というのは一見確かに合理的だ。だが離婚や親権をめぐる日米の考え方や制度の違いを知れば知るほど、日本がハーグ条約を批准しても問題は容易に解決しないのではないか、と思えてくる。
父親の子育てへの関与が大きい米国人
「米国の父親は日本と比べて、子育てへの関与の度合いがとにかく大きい」。米国で2人の子供を育てる知人は語る。確かに筆者のまわりをみても、平日でも学校に子供の送迎をする父親は珍しくないし、遠足など学校のイベントにも大勢の父親が顔を出す。子育ては両親でするもの、という意識が日本より浸透している。これは親権についての考え方にも反映されているようだ。
筆者の地元モントレーのベテラン離婚弁護士ゲイル・モートン氏は「離婚後も両親とclose continuous contact(親密かつ継続的な交流)を持つことが好ましい、という基本的考え方がある」と説明する。日本との根本的な違いとして、米国では共同親権(joint custody)が認められる。親権はlegal custody(法的監護)とphysical custody(身上監護)に分かれる。法的監護は子供の健康、教育、福祉に関して決定する権利義務、身上監護は子供と暮らす権利義務を指す。
米国では離婚の法制度は州ごとに定められており、国全体の状況を一般化することは難しい。以下は比較的リベラルなカリフォルニア州の状況になるが、モートン弁護士によると「法的監護については大半のケースで共同親権になる」と話す。これが単独親権になるのは、主に片方の親が子供に直接暴力をふるうケースなどだ。
つまり「母親に暴力をふるっていても、子供に暴力をふるっていなければ父親に親権が与えられる」(モートン氏)。また父親が子供に暴力をふるい、protection order(保護命令)が出されたケースでも、何年か経って保護命令が失効すれば、父親の申請によって共同法的監護が与えられる可能性がある。
身上監護についても状況は同じで「80%対20%、60%対40%など時間配分こそ違え、両方の親が子供と過ごす権利を得るケースが大半」(同)。
もう1つ、日本との違いは離婚における裁判所の関与だ。日本では2008年時点でも87.8%が協議離婚。つまり当事者同士が話し合い、役所に離婚届を出せば離婚成立だ。だが米国では裁判所に離婚を申請し、離婚判決を受ける必要がある。一部例外はあるが、その間に互いの資産、負債、収支を開示し、離婚合意書をまとめなければならない。
離婚協議は1度でおしまいにならない
子供がいる夫婦には養育計画の提出も義務付けられるが、モントレー郡の申請書を見るとその内容はとても細かい。学校の選択、宗教行事への参加、かかりつけ医師の選択、課外活動への参加、州外への旅行といった項目について、事前に他方の親の同意を必要とするかを選択する。しかもどちらかがその取り決めを破った場合、民事・刑事罰を課すか、それとも法的監護または身上監護を変更するかも記入する。
養育計画や財産分与は、弁護士を雇うなどして当事者同士の話し合いで決められるが、先述のモートン弁護士は「私の扱う案件で、当事者同士の話し合いがまとまるのは25%程度。残りは調停や裁判といった手続きまで進む。ほかの弁護士事務所でも割合は似たようなものだろう」と語る。内輪の話し合いではなく、“出るところに出て”離婚の条件を決める人が多いわけだ。
しかも離婚協議は1度やればおしまい、というものでもない。たとえば子供が幼いときに離婚し、身上監護において母親80%、父親20%と決まっても、子供が10歳くらいになり、父親が「これからは男親との交流が大切になる時期だ」として条件の見直しを申し立てれば、再び裁判所の決定をあおぐことになる。
筆者は6月初旬、モントレー郡家庭裁判所に足を運び、親権をめぐる審理を見学してきた。法廷内では20~30組の夫婦が順番を待っている。衆人環視のもと、1つの案件の審理にかけられる時間は10分程度。ある夫婦の場合、現在隔週で土曜日から日曜日夕方まで娘と過ごしている父親が「火曜日朝に子供を保育園に送るまで一緒にいたい」と申し立てをしていた。妻は「娘は今の状況に慣れている」と反論したが、あっという間に「月曜朝まで父親との滞在時間を延長する」という決定が出た。裁判官は事前に申請書を読み、互いの言い分を把握していたのだろうが、判決の理由などは一切説明されなかった。
もちろん家族のトラブルを、公的権力に頼ってきっちり解決するという手法にはメリットもある。日本では離婚すると、親権を持たない親が子供にまったく会えなくなるケースも多いが、米国では養育計画に反して他方の親に子供を会わせなかったりすると、親権が自分に不利に変えられてしまうリスクがある。冒頭紹介したテネシー州の男性のケースがその典型的な例で、子供を連れて日本に帰国した妻は米国では親権を失い、その後の裁判で多額の損害賠償を科された。
また厚生労働省の2006年全国母子世帯等調査結果報告によると、継続的に養育費を受け取っているケースはわずか19%にとどまる。一方、カリフォルニア州の場合、各郡の養育費サービス局に申し立てをすると、不払いの養育費回収に協力してもらえる。
容赦ない強制力により養育費の回収率高める
モートン弁護士によると、不払いの親には給与はもちろん失業手当まで差し押さえたり、運転免許証、弁護士免許、不動産業免許などの公的資格を停止してしまったりと容赦はない。例えばモントレー郡の養育費サービス局のウェブサイトを見ると、悪質な不払いと認められた父親に90日、6カ月の懲役刑を科すというプレスリリースが掲示されている。同郡の養育費回収率は2010年度には約60%だった。
離婚後、それぞれの親が子供に対して持つ権利と義務を裁判所命令という形ではっきりさせ、違反した親には罰則を科す米国。基本的に当事者同士の話し合いに委ねる日本。雇用における機会均等と同じ発想で、たとえ不倫の末に妻を捨てた夫でも子育てに関しては妻と平等。養育の権利もコスト負担も母親1人で抱え込む日本とは大違いだ。
その極端な制度的・心理的な落差が、米国人をしてabductionとまで言わしめるトラブルの根っこにあると言えそうだ。たとえ日本が共同親権を認めるなど国内法制度を整え、ハーグ条約を批准したとしても、この差は容易には埋まらないのではないか。