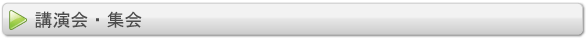【2017.04.15】 親子ネットレポート『親子断絶防止への期待と今後の展望 ~改めて考えたい「子どもの最善の利益」~』
親子ネットでは、4月15日に「親子断絶防止法への期待と今後の展望」と題して講演会を開催しました。
「親子断絶防止法」の法案が検討される中、重要な課題の一つとなっているのが「子どもの最善の利益」とは何かという事で、夫婦間の紛争の中では正反対の見解が出てくるところでもありました。
そこで、今回は講演会の副題を「改めて考えたい子どもの最善の利益」として、各分野の専門家の先生方に様々な視点からご講演をして頂きました。
はじめに

140名以上の方が来場されました
講演に先立ち、親子ネット佐々木代表より、「法案に反対する意見もあるが、私たちが負ける事はない。なぜなら、離婚、別居後も両親が子の養育に義務を持つ自覚をもち、親が子を想う気持ち、子が親を想う気持ちを尊重することは、だれも否定できない、自然の権利、人としての自然な愛情の発露だからです。負けるというのは子どもと会うことを諦めた時のことを指す。子どもを愛し続け、活動していきましょう。」と開会の言葉を述べられました。
続けて、自民党の城内実衆議院議員からは、「憲法には、法の下の平等、幸福追求権もある。連れ去った側が幸福追求権を声高に主張するのはおかしい。また、特に家裁における司法による救済という面では不十分、法案をしっかり通していかなければならない」とお話しいただきました。
また、⺠進党の真山勇一参議院議員からは、「親子断絶防止法案に反対されている方々の意見も様々だが、DVがあるからとする意見はDVの表明が一方的であると気づいた。子どもの最善の利益のためには、離婚・子どものことを考え、具体的なケースを役所にぶつけながら、法律のみならず仕組みづくりも考えていく必要がある」とお話しいただきました。
棚瀬孝雄先生の講演要旨
最初の講演者である棚瀬孝雄先生からは、「親子断絶防止法の意義と実施の留意点」について、法律家として理論的な面からご講演頂きました。以下その要旨となります。
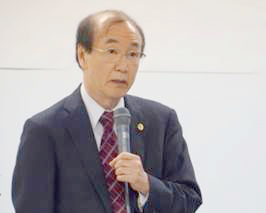
ご講演される棚瀬孝雄先生
法案がまだ可決されないなか、主な反対論の一つとして、非監護親のDVや虐待が理由にされている。
米国はじめ他国でもDVの存在は変わらないが、DV等のある場合には厳しく対処されている。
国内では、ことさらDVが強調されているが、これを理由に面会交流を制限するのはおかしいし、適切に対応が可能である。
これまで、家族法に実務上のルールが存在しないため当事者の協議任せになっていた。
家裁実務の中では現状追認のロジックが重視され監護親重視となっているが、今回の法案は基本法として、これらの問題に指針を与えるものとなる。
従来、国内では原則は弱く、例外が多かった。また、「子の意思の確認」が面会交流をしなくて良い「例外」として濫用されているが、子の意思は、別居・離婚の過程の中で歪められる。
子の意思は、監護親の意思を「子の」名を使い押し付けるものであり、こうしたことが起こりうる環境をつくる親にこそ問題があるが、例外が主張される場合も立証責任を伴っていなかった。
さらに、面会交流を行う場合にも、どこまで実施すべきか明らかにされていなかった。
法案では、面会交流を行うことを原則として、これら3つの問題に指針を与え、家裁実務上でも当事者の説得が容易になる。
このように、本法案は家裁実務に、方向性を示すものとなっており、これを実定法にして裁判所のルールとしてもらう必要がある。
夫婦の別れは、決して親子の別れとなるべきものではなく、法案はこの問題に本気で取り組む政治の決意である。
小田切紀子先生の講演要旨
次に、人間社会学部教授でおられます小田切紀子先生より、「親の紛争と子ども」と題して、主に子どもの意思とは何かということについてご講演いただきました。以下、その要旨となります。

ご講演される小田切紀子先生
諸外国ではスタンダードとなっている離婚後の共同養育をどう実現すればよいか研究してきた。
監護親と非監護親は対等な立場ではないが、その中で、児童権利条約の「子どもの意思」が濫用されてきている。
子どもがもう会いたくないという場合には、「DVがある場合」、「子どもが親の離婚や将来のことで混乱している場合」、「離婚・別居後、ほとんど会っていない場合」、「子どもが別居親を忠誠葛藤や罪の意識なく批判している場合」という4つのケースにつき考える必要がある。
後者二点では、監護者が子どもをコントロールしているか、片親疎外症候群の可能性がある。
監護親が、子どもをコントロールしている場合には、子どもが監護親から離れた後、支配されていたことに気づき、監護親を拒絶するケースもある。
子どもが会いたくないと言うと、面会交流が中断される事は良くあるが、これは子どもの虐待することにもなりかねない。
子ども自身の発言により面会交流ができなくなった場合、後で子どもは自分自身を責め続けることにもなる。
子どもの発言によって、人生に関わることに責任を負わせてはならず、家裁調査官等きちんとトレーニングを受けた人が子どもの意思を聞き、どうするかは大人に任せることが、子どもの意思を尊重することにつながる。
丸井妙子先生の講演要旨
次に、「子どもを犠牲にしない離婚と養育の方法」についての翻訳本を出版された丸井妙子先生からは、これまでのご経験を元に、以下のようなアドバイスを頂きました。

ご講演される丸井妙子先生
近年、家裁の現場でも面会交流の実施を原則とするようになってきているが、親の離婚に際しては、子どもの気持ちは様々で、悲しむ子も多いが、ほっとする子もいる。
面会交流を進めるにあたっては、親同志の別れる前の関係性が問題となってくるが、事実よりも主観でどうかということが影響する。
面会交流は親の欲求を満足させるためのものではなく、子どもの幸せのためのもので、別居親が怒りの感情を強く持っているとうまくいかない。感情を抑えることも大切。
第三者を交えて話し合うときには、一般論を述べるのではなく、感情的にならず、ご本人の個別の事情のみを述べるのがよい。
子どものことを易しく丁寧に話し、親としてふさわしい態度で臨むとよい。
野沢慎司先生の講演要旨
社会学部教授の野沢慎司先生からは、ステップファミリーの研究を長年続けてこられたご経験から、本法案に関連して見えてきたこと、とりわけ、法案に関するいくつかの疑問についてお話されました。
疑問点の一つ目は、「離婚をするとなぜ半分のひとは親権を失うのか?」ということです。

ご講演される野沢慎司先生
他国では制度が変わってきた。
協議離婚がほとんどのニュージーランドでも共同親権、共同養育を推進している。
国内では、親権を持つ親が再婚する際には、非監護親には尋ねる必要もなく、養子縁組が簡単にできてしまう。
さらに、親の離婚を経験した子どもに社会は何を保証すべきかの議論もない。
離婚をしてしまうと、単独親権しか認められず、共同親権が選べない現状は、子どもの権利条約に反していると感じている。
近年では、子どもの育児に関わる事が当然だというキャンペーンがあるが、それが、離婚したとたんに矛盾した状況に陥るが故に紛争が激化している。
これを放置して良いのか?
親が離婚していても、いなくても、子どもがDVや虐待から守られる法整備は必要。
面会交流の話とは切り離して考え、親子関係が失われない社会制度への改革を要する。
離婚後の親子関係の形態として2つのモデルがあることを提唱している。
一つは、スクラップ&ビルド型で、離別により片方の親が除籍され、新たな一人親家庭が作られる、日本では「親子より婚姻が優先される」この関係が主流。
一方で、海外では、離婚後も家族はネットワークとして存在し、複数世帯にまたがるネットワーク型がある。
2011年の民法改正以降、この考え方が入ってきており、社会的にも支持される割合が増えている。
この型では、対立・競合関係が生じる場合もあるが、これを解消するのが社会的課題となっている。
これからは、これまでの家族観を変えて、実の親がサポートしながら、継親が緩く関わっていくのが良いと思われる。
しばはし聡子先生の講演要旨
ご講演の最後には、離婚・面会交流コンサルタントのしばはし聡子先生より、「法律とこころ」と題して、ご自身の経験も踏まえながら、離婚の後に監護親としてどのような気持ちで面会交流に臨んだか、法案に対してどのように思うかご講演頂きました。

ご講演されるしばはし聡子先生
離婚の後、面会交流のことはあまり考えていなかった。
当初は、面会交流をすることにより夫を喜ばせたくなかったし、子どもに悪口を言われる不安もあった。
また、連絡のやり取りも大きなストレスであった。
しかし、実際にやってみると、夫との関係も前より良くなった。
法案が通り面会交流が当たり前との認識が浸透することが大切。
ただ、法律ができても親の気持ちが変わらなければ、何も変わらない。
また、子どもが小さいと、子どもは親子の架け橋となることを強いられ、これは重い責任を負わせることになる。
離婚しても、親同士、親子の関係は続くものであるが、知識をつけ理論武装して相手に対応するのであれば、相手も弁護士に頼らざるを得ず、直接のやり取りもできなくなる。
心持ちを整え、相手を責めるのではなく、寄り添うことが大切である。
法案のことに関しても、賛成派・反対派とまるで夫婦間の紛争の事の様に感じる。
自分自身が変わること、歩みよる姿勢を示せば、何かが変わるかもしれない。
おわりに
講演録としては、以上となりますが、様々な視点から、法案とそれを取り巻く現状、あるいは根本的問題点につき詳しくご講演頂き大変参考になりました。
親子ネットしても、続けて、勉強会を開催してまいりたいと思います。ご期待ください。