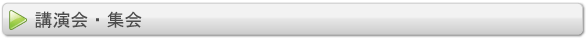【2016.06.11】 親子ネットレポート「親権紛争におけるフレンドリー・ペアレントルール(寛容性の原則)の将来展望 ~国内初!千葉家裁による面会交流による面会交流に寛大なる別居親に親権を求めた判決から~」
1.はじめに
平成28年6月11日、親子ネットは「親権紛争におけるフレンドリー・ペアレントルール(寛容性の原則)の将来展望 〜国内初!千葉家裁による国会交流に寛大な別居親に親権を認めた判決から〜」と題した講演会を豊島区民センターにて開催いたしました。
平成28年3月29日、千葉家庭裁判所松戸支部において、親権者決定に「フレンドリー・ペアレントルール※」を明確に採用した判決が下されました。この訴訟は、夫婦の別居に伴い、幼い娘を妻に連れて行かれ、約5年間面会させてもらえなかった父親が娘の「親権」などを巡って母親と争っていた離婚裁判で、裁判所が父親を親権者と認める判決を出した画期的な決定です。
これまで重視されてきた「継続性の原則(子どもが住んでいる環境を変えない方が子どもの福祉に適うという司法判断で、子どもの連れ去り、引き離しを誘発させていた)」から「フレンドリー・ペアレントルール」へ大きく舵を切った今回の司法による判断は、今後の家裁実務にも大きな影響を与えるものと思われます。
本講演会では、講師として、本訴訟代理人である上野晃弁護士、先進諸国の離婚後の諸制度を研究されている小田切紀子教授をお招きしてご講演をいただきました。その後、有識者によるパネルディスカッションにて、今後の「フレンドリー・ペアレントルール」の将来展望を議論いただきましたので、ここにご報告いたします。
2.基調講演1「千葉家裁松戸支部でのフレンドリー・ペアレント判決に関して」

弁護士 上野 晃 先生
3月29日に千葉家裁松戸支部において、フレンドリー・ペアレント判決が下された際、多くのマスコミに掲載され、反響の大きさに驚いたと同時に、世の中に困っている方・問題と思われている方がどれだけ多いかということを実感したと言う上野先生。
議連の総会に足を運んだ時、記者の方より「実は私も当事者です。頑張ってください。」と言われ、この判決が待ち望まれていたことを肌で感じられたとのことです。本基調講演において、フレンドリー・ペアレント判決の経緯と意義、そして、今後の展望について、本訴訟の代理人を務められた上野先生よりお話を頂きました。
当事者のみなさんが裁判所の門を叩く時、ほとんどの方は裁判所の正義を信じ、困った人を助けてくれると信じていたはずです。しかし、ほぼ全員の裁判官が、目の前の個別事情を見ないまま、金太郎飴のように判決を下しているという不条理を繰り返しています。この背後には裁判所のお役所体質が存在し、裁判官は上の評価を気にするあまり、横並びでない判決を避ける傾向があり、他の裁判官と同じ判決を出してさえいれば、罪の意識を持たなくて済むことを上野先生は指摘されました。
本訴訟において、真の相手とすべきはこの裁判官であり、フレンドリー・ペアレントルールの議論の矛先を裁判官に持っていくことが肝要であったと上野先生は振り返ります。
今回の判決は、裁判所が母と子の親子関係に問題があると認定したものではなく、親と子の人間関係を形成することに重きが置かれた結果であると言えます。相手方は、争いにより正しい方が親権を得る必要があると主張していましたが、弁護側にはどちらが正しいという考えはなく、両親が共にしっかりと子どもの成長に関わることが必要であるとの主張を続けていました。松戸支部は後者の主張を支持し、子の親権者を決定する上で、両方の親からの愛情をきちんと育む環境を整えているのはどちらであるのかを判断している点が画期的なのです。
離婚に際して同居親(監護親)を決定する際には、別居親の存在を肯定的に子どもに伝えられるか、別居親と子どもの面会交流に協力出来るかなどの寛容性を同居親としての適正と判断される原則。『友好的親条項』あるいは『非監護親に対する寛容性の原則』とも呼ばれ、別居親と友好関係を保てる親を同居親決定の際は優先することを意味している。
今後、当事者のみなさんには「共同養育計画」を作ってもらいたいと上野先生は言います。離婚後の養育比率が現在の100:0から60:40くらいとなれば、相手に親権を渡しても良いという考えが出やすくなり、無用な争いもなくなると考えられるそうです。
最後に、上野先生は、「世の中は私たちの希望している方向に動くと確信しています。なぜならば、私たちには正義があると考えるからです」という心強いお言葉にて、ご講演を締め括られました。
3.基調講演2「先進諸国におけるフレンドリー・ペアレントルール」

東京国際大学教授 小田切 紀子 先生
小田切先生は、親が離婚した子どもをサポートするため、20年ほど前から子ども支援のグループを立ち上げられており、また、ハーグ条約のもとで弁護士と組んで裁判外紛争解決手続(ADR)にも参画されています。今回のご講演では、フレンドリー・ペアレントルールを客観的に見た上で、本ルールが諸外国においてどう取り入れられているか、ご研究された成果をご発表頂きました。
本ルールは素晴らしいものでありますが、だからこそ、子どもの監護権を決める判断材料の1つであり、「子の最善の利益」と同様に適切に利用されるべきと小田切先生は指摘します。本ルールが過大に評価されることにより、DVや児童虐待を行う親に親権が移る恐れがあるからです。
日本では、証言のみによりDVが容易に認定される場合にありますが、裁判では事実関係の立証が重要であり、監護者を決める過程で適切にアセスメントすることが本ルールの適用において重要だと述べられました。米国では、DVや児童虐待の事実関係がある場合は本ルールの適用は除外されますので、実証に基づく適切な判断が必要なのです。
諸外国の状況として、米国では共同養育の判断基準の1つとして本ルールが位置づけられており、特に、東海岸・西海岸エリアにおいて運用が進んでいます。イギリスも米国と同様、離婚後の子どもの養育は親の責任、親に会えることは子どもの権利としています。ドイツでは、両親のみならず祖父母や兄弟姉妹との交流も認められることが明文化されており、フランスでは非同居親に訪問権や宿泊権が付与されており、子どもに危険が及ばない限り面会交流を拒否することはできません。
日本に共同養育を浸透させるにあたり、今後、協議離婚の中に親教育プログラムの導入を義務付け、共同養育計画書の作成を促すことがテーマであると言う小田切先生。現在、先生は兵庫県明石市と連携して活動をされていますが、首長が変わると政策が大きく変わることもあるため、政権に左右されずに継続することが大切であり、共同養育の実現に向けた活動の輪を広げて行きたいと決意を新たにされました。
4.パネルディスカッション

左)小田切紀子先生
中央)三谷英弘前衆議院議員
右)しばはし聡子先生
先生、離婚・面会交流コンサルタントのしばはし聡子先生、弁護士の杉山程彦先生をお迎えし、親子ネット代表の佐々木を加えた6人にて、フレンドリー・ペアレントルールを考えるパネルディスカッションを実施いたしました。
本ルールのメリットについて、弁護士の立場からのご意見として、杉山先生からは子どもの連れ去り抑止につながること、そして、上野先生からは不要な紛争が軽減し、子どもにとっては何のデメリットが無いという点が挙げられました。三谷先生からは、立法に携わった立場から、このようなフレンドリーペアレント判決が重なることで、司法と立法との距離が縮まり、本ルールを法律に落としむ可能性が高まるというコメントを頂きました。

左)親子ネット代表佐々木昇
中央)杉山程彦弁護士
右)上野晃弁護士
一方、しばはし先生からは同居親の視点より、子どもに対する影響力の強い同居親こそがフレンドリーペアレントの意義を理解し、自らの責任を果たすことが大切であると主張されました。そして、小田切先生は子どもの心理学的な観点より、子どもの片親阻害を防止するためにも、本ルールに基づいた離婚時の養育計画書の作成と面会交流の実施が必要であると指摘されました。
先生方の発言を受け、親子ネット代表の佐々木は当事者の立場より、離婚した元配偶者は子どもの母親であるという認識を持ち続けることが大切であると述べました。
5.おわりに

渡辺喜美先生と登壇者の皆様
このたびは、講師、登壇者、親子ネット会員の皆様方より様々な形でご協力を頂き、このように盛大な講演会が開催できましたことを、心より感謝申し上げます。また、講演会の最後には、参議院議員の渡辺喜美先生よりご挨拶をいただきました。
ご多用のところ足をお運びくださいました議員の先生方、自治体関係者の皆様をはじめ、ご参加くださいました皆様方に、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。