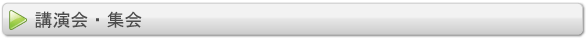【2016.03.26】 親子ネットレポート「実例から学ぶ離婚後の共同養育のあり方 〜実例報告と臨床心理士・法律家からの提言〜」
1.はじめに
平成28年3月26日(土)、親子ネットは「実例から学ぶ離婚後の共同養育のあり方 〜実例報告と臨床心理士・法律家からの提言〜」と題した講演会を、上智大学目白聖母キャンパスにて開催いたしました。
開催にあたり、高村正彦自由民主党副総裁から祝電をいただきました。
【高村正彦自由民主党副総裁からの祝電】
(画像をクリックするとpdfファイルでご覧いただけます。)
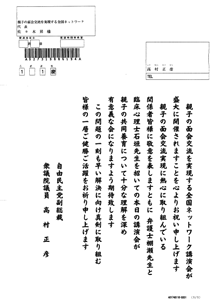
 離婚後の子どもの養育について、欧米諸国は共同親権(監護)を採用している一方で、日本は単独親権制度を固守し、家族法の未整備と裁判所の不適切な運用により、親子の面会交流や養育費の支払いが適切な形で行われず、子どもの精神的、経済的な貧困・孤立などの問題が多々発生しています。このような状況の改善に向け、平成26年3月18日に親子断絶防止議員連盟が設立され、「面会交流の拡充」や「養育計画の作成義務化」などを骨子とする「親子断絶防止法」の早期成立を目指しています。
離婚後の子どもの養育について、欧米諸国は共同親権(監護)を採用している一方で、日本は単独親権制度を固守し、家族法の未整備と裁判所の不適切な運用により、親子の面会交流や養育費の支払いが適切な形で行われず、子どもの精神的、経済的な貧困・孤立などの問題が多々発生しています。このような状況の改善に向け、平成26年3月18日に親子断絶防止議員連盟が設立され、「面会交流の拡充」や「養育計画の作成義務化」などを骨子とする「親子断絶防止法」の早期成立を目指しています。
今回の講演会は、離婚後も共同養育を実践されている元ご夫婦より実例をご紹介頂いた上で、臨床心理士の石垣秀之先生、弁護士の棚瀬孝雄先生をお招きし、離婚後の共同養育のあり方をテーマにご講演を頂きました。ご参加くださいました皆様方と、広く離婚後の子どもの最善の利益を考える機会となりましたので、講演会の概要についてご報告いたします。
2.共同養育実践者からの実例報告1(DVD上映)
親子ネットは、お子様が10歳の時に離婚された後も、共同養育を実践され、現在21歳になられた息子さんをお持ちのお母様にインタビューさせて頂き、その模様をDVDで上映しました。
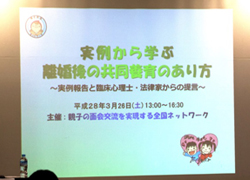 離婚にあたり、子どもに関しての夫婦喧嘩はなく、面会交流の取り決めもしなかったそうです。その根底には、「離婚は子どもを悲しませてしまうので、それ以外のことでは、子どもを悲しませたくなかった」という思いがあると言います。
離婚にあたり、子どもに関しての夫婦喧嘩はなく、面会交流の取り決めもしなかったそうです。その根底には、「離婚は子どもを悲しませてしまうので、それ以外のことでは、子どもを悲しませたくなかった」という思いがあると言います。
離婚後も、元配偶者に対する感情のしこりや、お子様に会わせることへの抵抗感は全くなかったとのこと。3人で食事をしたり、映画に行かれていたことをご紹介頂きました。お子様とお父様・お母様とのご関係は、今でも良好だそうです。「離婚しても家族」という言葉が非常に印象的でした。
3.共同養育実践者からの実例報告2(ご講演)
次に、離婚後もお子様の共同養育を実践されている元ご夫婦にご登壇頂きました。まずは、お父様より、離婚の経緯と共同養育における人間関係の構築を中心にお話を頂きました。
離婚に際してお父様は、自分の子どもが他人に対して危害を加えた場合、自分に全く責任がないとは言えないと思い、母親である元妻との人間関係の構築が大事だと感じられたそうです。共同養育を実践しようと言葉で思われたことはないものの、離婚後に父親とコンタクトがとれなければ、子どもが大学に進学できなくなるのではとの不安を抱かれたと言います。自分の子どもの未来を全て想定して事前に取り決めることはできないので、お子様と会う頻度についての契約などはなく、お子様が「会いたい」というのであれば常に会うことができ、お子様に「愛している」と常に言うことができる状態だそうです。そのため、離婚後も環境に合わせた状態でお二人で話し合いを持たれており、現在は、元妻は他人でありながらも家族のような存在で、良い距離感で連絡を取り合い、お互いに支え合っていると感じると仰られました。
続いて、お母様より、離婚における家族のあり方についてのお話を頂きました。離婚当初は、元夫にお子様を会わせたくない、近寄らせたくないと思われていたそうです。しかし、お子様はやはりお父様に似ており、元夫を嫌いなままでいると、お子様を100%愛せなくなってしまうのではないかという恐怖から、離婚後も元夫と仲良くしようと決意されたと言います。子連れで離婚した者の立場から、離婚は子どもの将来を変えてしまう重大な決断であり、子どもが被害者とならないためにも、相手を恨んだ状態で離婚することはやめて欲しいと伝えられました。
4.共同養育のあり方・臨床心理士からの提言
 講演会の後半は、臨床心理士の石垣秀之先生より「親に会えないことで起こる子どもへの影響」と題したご講演を頂きました。石垣先生は、スクールカウンセラーとして子どもたちにカウンセリングやトラウマ治療を行う中で、問題行動を起こす子どもの多くが離婚や家庭の問題を抱えていることに気付かれたと言います。子どもによっては、親の離婚により、身体症状があらわれる程のトラウマ反応を示す場合もあるそうです。トラウマ反応は、自分の命が脅かされるような経験により引き起こされることが分かっており、子どもにとって親の離婚は、そのくらい重大なインパクトをもたらす出来事であると石垣先生は指摘します。
講演会の後半は、臨床心理士の石垣秀之先生より「親に会えないことで起こる子どもへの影響」と題したご講演を頂きました。石垣先生は、スクールカウンセラーとして子どもたちにカウンセリングやトラウマ治療を行う中で、問題行動を起こす子どもの多くが離婚や家庭の問題を抱えていることに気付かれたと言います。子どもによっては、親の離婚により、身体症状があらわれる程のトラウマ反応を示す場合もあるそうです。トラウマ反応は、自分の命が脅かされるような経験により引き起こされることが分かっており、子どもにとって親の離婚は、そのくらい重大なインパクトをもたらす出来事であると石垣先生は指摘します。
修復不可能な夫婦関係の悪化により、子どもが一方的に連れ去られる問題についても石垣先生は言及されました。親との引き離しにより、子どもは悲嘆反応を示し、自我を守る反応が生じます。そして、別居親に会えなくなると、同居親にも見捨てられると拡大解釈し、不安定になります。このような状況で自分が生き残るために、同居親の気持ちを逆撫でしないようにつとめようとするのです。
このような状況に子どもが陥らないためにも、連れ去りが生じないような社会にしていくことは極めて重要です。石垣先生は、連れ去りに関する社会的認知が広まれば、連れ去る前に調停手続きや各種のサービスを受けられるようになるのではないかと提言されました。
5.共同養育のあり方・法律家からの提言
 続いて、京都大学名誉教授であり弁護士の棚瀬孝雄先生より「面会交流確保の闘い」をテーマに、ご講演を頂きました。棚瀬先生は、子どもが連れ去られた後の面会交流を確保する努力を続けられています。しかし、裁判所は面会交流に対して、今でも消極的であり、弁護士として面会制限の論理そのものが間違えていると反駁しているが、事実そのものが歪められてしまうこともあり、なかなか通らない現実があると伝えられました。
続いて、京都大学名誉教授であり弁護士の棚瀬孝雄先生より「面会交流確保の闘い」をテーマに、ご講演を頂きました。棚瀬先生は、子どもが連れ去られた後の面会交流を確保する努力を続けられています。しかし、裁判所は面会交流に対して、今でも消極的であり、弁護士として面会制限の論理そのものが間違えていると反駁しているが、事実そのものが歪められてしまうこともあり、なかなか通らない現実があると伝えられました。
親の別居や離婚は、子どもにとって天地がひっくり返るほどの体験であり、母子家庭や父子家庭の子どもは、両親の家庭の子どもより何倍も不登校に陥り、非行に走りやすい傾向にあると言います。連れ去り前の子どもと親との関係は良好であるため、切り離す理由はないと裁判所が判断すれば良いだけであり、極めて単純であるにも関わらず、裁判所は面会交流を実施する理由として全く取り上げないそうです。
このような面会制限の論理の背後には、法的な議論として高められた論理ではなく、今の形の制限的な面会交流を良しとして必然化する、司法官僚的な発想が蔓延していると棚瀬先生は述べられました。
一方で、自分が子どもを連れ去られるまでは、こんなことが起こるとは思わなかった、日本にこのような問題があるとは知らなかったと言う当事者も多く、親子ネットの運動やマスコミの報道はあるものの、本当に悲惨な状態はメディアを通して社会に伝わっておらず、社会的認知の問題が存在することにも言及されました。
過去の日本の家庭において、男性が女性を抑圧してきた背景があり、離婚には女性を開放するという側面もありましたが、現在は開放の域を超えて、逆に乱用されているのではないかと棚瀬先生は指摘されます。しかし、かつてのように、男性が家庭の中で抑圧的である時代は終わり、社会は少しずつ動いています。これから制度に切り込む形で社会や政策に働きかけ、現状を変えていかなければならないと語られ、ご講演を締め括られました。
講演後の質疑応答では、共同養育を実践されている元ご夫婦に対して、離婚時の自身の葛藤や、子どもに対する離婚の説明の仕方などの質問がありました。また、石垣先生には、離婚回避に向けた臨床心理士のサポート内容や子どもの忠誠葛藤を見抜く方法など、棚瀬先生には、離婚前に単独親権状態になっている状況や面会交流のプロセスに関する質問などが寄せられ、1つ1つの質問に対して、登壇者の皆様方より丁寧なご回答を頂きました。
6.おわりに
このたびは、講師、登壇者、親子ネット会員の皆様方より様々な形でご協力を頂き、このように盛大な講演会が開催できましたことを、親子ネット運営委員一同、心より感謝申し上げます。また、ご多用のところご来場くださいました議員の先生方、自治体関係者の皆様をはじめ、ご参加くださいました皆様方に、厚く御礼申し上げます。