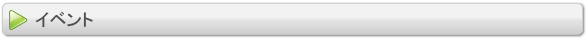【2017.03.02】 親子断絶防止法 全国連絡会主催 「子どもの最善の利益を考える国会勉強会」参加報告
平成29年3月2日、親子断絶防止法 全国連絡会は「子どもの最善の利益を考える国会勉強会」を開催いたしました。本勉強会に親子ネットとして参加してまいりましたので、参加のご報告をいたします。
冒頭、親子断絶の当事者を代表し、まだ幼いお子様と引き離されてしまった女性当事者より、法の未整備が原因であるために、健全な母子の交流と絆の形成が妨げられていること、そして、親子断絶防止法の成立に寄せる強い思いが披露されました。
続いて、親子断絶防止議員連盟 会長の保岡 興治 衆議院議員、親子断絶防止議員連盟 事務局長の馳 浩 衆議院議員より、ご挨拶を賜り、親子断絶防止法の成立に向けたご活動内容についてご説明をいただきました。また、国会会期中のお忙しい中、多くの国会議員の先生方が本国会勉強会に足を運んでくださいました。

ご挨拶される 保岡 興治 衆議院議員

ご挨拶される 馳 浩 衆議院議員
本国会勉強会は3名の有識者の先生方にご登壇をいただき、親子断絶の現状を踏まえた上で、「子どもの最善の利益とは何か」について、国会議員の先生方にご理解いただくことを目的とし、開催されました。
講演①「親子断絶防止法成立の意義と目指すべき姿」棚瀬 孝雄 弁護士
棚瀬弁護士は、親子断絶防止法がどのような点で優れているのかについて、ご説明されました。
夫婦が離婚しても、父母と子どもとの関係が残されなければいけないことが大前提としてあります。
これは、離婚に関して子どもには責任がなく、片親と断絶されることで将来の対人関係に影響が及ぼされるなど、離婚の傷を子どもが生涯負ってしまう可能性があるからです。
本法案は、この点についてはっきりと示す「基本理念」が優れていると述べられました。そして、棚瀬弁護士は本法案を「理念法」ではなく、裁判の規範として使われるべき「基本法」であると位置づけています。
日本の家族法の特徴として、家庭の問題は複雑であるため、法は介入せず当事者間で協議した方がよい、あるいは、調停が設置されて審判に移行しても、基本的には合意可能性を探るなど調整が中心になっています。
面会交流に関しては、民法766条が改正され、面会交流についても言及されています。
その内容として、当事者同士の協議で決定し、当事者同士で決められない場合は家庭裁判所が決定するとありますが、どう決めるのかは全く定められていません。
ただ「子の最善の利益」に配慮すると書かれているのみです。しかし、「子の最善の利益」に関して解釈が異なるケースが多く見受けられるそうです。
この点に関し親子断絶防止法においては、「子と父母との継続的な関係の維持」と示され、当初の法案の第7条では「親子としての緊密な関係が維持されること」と示されています。(注;12/13付修正案では緊密→良好に修正されました)
日本でよくみられる離婚後の別居親との「月に1回2時間」の面会交流は、緊密(良好)な関係・継続的な関係にはあたらないと棚瀬弁護士は主張されます。
月2時間は0.3%の時間しか占めません。99.7%の時間は別居親がいない生活となるのです。
親子断絶防止法の本条項により、そのような希薄な面会交流が審判で出されることを阻止できると期待されるそうです。
また、当初の法案の第1条では、面会交流について「子の健全な成長及び人格の形成のために重要である」と述べており、これは裏を返せば、「子の健全な成長及び人格の形成のために」なるようなものでなければ「面会交流」ではないということになります。
すなわち、欧米における月2回程度の宿泊交流のように、様々な生活の場面で親子が暮らし、別居親の愛情を受けることが求められるとのことです。(注;子の健全な成長及び人格の形成のために重要であるとの記述は12/13付修正案では削除されており、残念です。)

ご講演される 棚橋 孝雄 弁護士(右端)
また、国・自治体の責務を明らかとした第6条では、離婚届提出の際に養育費と面会交流を取り決めること、第8条には連れ去り防止と事後的な対応、国・自治体が啓発や支援を行うスキームが盛り込まれています。
行政がこの問題に関与する際には、この2つを両輪で取り組んで欲しいという思いを述べられました。
第9条の虐待・DV、子の最善の利益を害するおそれについては、「特別の配慮」における原則と例外のうち、例外が肥大化しすぎることが懸念されると指摘されます。
DV被害にも様々な態様があり、それが面会交流を妨げる理由となり得るのかについて、裁判官は正面から向き合い、親と子どもとが不必要に切り離されることがないようにすることが必要だと述べられました。
また、子どもの意思の表明に関しては、子どもに対して同居親か別居親かの択一を迫ることは、子に踏み絵を踏ませるようなものであるとして、反対の立場をはっきりと示されました。
「子の最善の利益」は子どもが判断するものではなく、周りの大人たちが子どものために判断するものであることを強く主張されました。
講演②「子どもの最善の利益と良好な親イメージ」山口 豊氏 東京情報大学准教授
山口先生は臨床心理学的な立場より、片親疎外(PA)と子どもの最善に利益についてご発表されました。
まず、片親疎外は日本でほとんど研究がされておらず、社会に浸透していない原因でもあると述べられました。
片親疎外とは、同居親と子どもが一体化して別居親を拒絶する状況を言い、米国では1980年代にリチャード・A・ガードナー精神科医が「片親疎外症候群」を提唱しています。
また、米国における「子の監護評価者に期待されるトレーニング」の範囲として、ドメスティック・バイオレンスや児童への性的虐待と同列に「片親疎外」の項目が含まれているのだそうです。
米国の司法省ウェブサイトにも、子どもとの関係を妨害することは情緒的虐待であることが示されており、PAの浸透が日本と大きく異なっています。
次に山口先生は、片親疎外が子どもに与える心理的な影響についてご説明されました。
報告されている論文によると、片親疎外を受けた子どもは、自己肯定感の低下、人間関係の構築困難、不安・抑うつ・不眠・食欲不振・気力の低下・自殺念慮などの傾向が見られることが分かっています。
また、面会交流の有無による神経症の発症傾向を比較すると、面会交流をしている子どもたちの方が精神的に安定している傾向が見られています。
これらの原因について山口先生は、子どもの自己イメージは親に対するイメージに大きく影響を受けるため、親のイメージが悪いと子どもの自己肯定感につながらないと指摘されます。
そのため、子どもと親との関係性を良好にするための心理的な支援が必要であることを述べられました。

国会勉強会の様子
そして、片親疎外(PA) が生じるメカニズムについては、同居親が別居親に対する嫌悪感を示している場合、子どもは自身の心理的なバランスを保つため、自らも別居親を拒絶することで、心理的な均衡を得るのだそうです。
また、たとえ親が別居親を言葉で拒絶しなくても、同居親の表情により、子どもは親の心理を察知し、PAになるのではないかと考えています。
これらのことから、片親疎外は、子どもには精神的虐待となり、同居親には子育てのストレス要因となり、別居親には怒りと絶望を引き起こすことから、 「誰をも幸せにしない」と述べられました。
そこで、山口先生は「子の最善の利益」のために、親同士の葛藤を軽減し、関係性を良好にするための心理支援や面会交流支援、共同親権体制への法整備が必要と強調されました。
講演③「子どもの記憶は鵜呑みにしない:幼児性健忘と偽記憶」宮川 剛氏 藤田保健衛生大学総合医科学研究所教授
宮川先生は、ネズミと人を対象として遺伝子と心の関係についての研究をされています。
今回のご講演では、子どもの「意思」は信用できるか?というテーマにてご発表をされました。
大人の人を対象とした記憶に関するアンケート結果によると、思い出すことのできる最も古い記憶は3-4歳前後であると答える人が最も多く、幼児の頃のエピソード記憶は忘れさられる傾向にあることが分かっています。
では、ネズミはどうかというと、電気ショックを与えられた大人のネズミは、1ヶ月経った後でもその場所のことを覚えており、すくみ反応を示すことが分かっています。
しかし、子どものネズミは1日後には覚えているものの、1ヶ月経つとほとんど忘れてしまうのだそうです。
これは、子どもの脳では新しい神経細胞が活発に作られていることによります。
脳の海馬において新しい神経細胞が作られると、古い記憶の神経回路を壊し、上書きしてしまうからです。
これが、幼児性健忘が生じるメカニズムであると宮川先生は考察されます。
また、大人のネズミでもランニングや抗うつ薬の投与により新しい神経細胞が生まれ、さらには、記憶したことを忘れやすくなることが報告されています。
そのため、会場にいらしている多くの当事者の方々に対して、忘れたい記憶がある方はランニングや運動をすることをおすすめすると宮川先生は仰いました。
次に、記憶に関するアンケート結果にもどり、0歳や1歳の頃の記憶があるという人のデータに注目されました。
この頃の記憶を覚えていることは考えにくいため、「偽記憶」なのではないかと宮川先生は指摘されます。
気球に乗っている人の顔写真を子どもの頃の被験者の写真にすり替えて被験者に見せるという実験では、半数の方が「子どもの頃に気球に乗った時の記憶を思い出した」と言い、さらには気球に乗ったときのことを説明し始めるのだそうです。
この結果から言えることは、「人に偽の記憶を植え付けることは容易である」ということです。
同様に、ネズミに対してもニセの記憶を植え付けることに成功していることから、ネズミと人とに共通した生物学的事実と言えるそうです。
最後に宮川先生は、ハイダーの認知的バランス理論に触れられました。
父親、母親、子どもは三角関係にあり、「安定」と「不安定」の2つの状態に分けることができます。
人間は「不安定」な状態であることを嫌うため、「安定」な状態へ向かう心理的な力が働きます。
子どもが父親、母親に対してプラスの関係性であるにもかかわらず、両親がマイナスの関係性である場合は、この三角関係が「不安定」となり、子どもは「安定」な関係性を求める中で、片親とのみ同居している状況下では、別居親との関係性を悪くせざるを得なくなるのだそうです。
このような関係性に幼児性健忘や記憶の植え付けが加わると、偽の記憶により別居親とのプラスの記憶がマイナスに転じることが必然的に生じてしまうことになってしまうのです。
よって、子どもの話を聞くことは大事であるが、事実とは限らないことがあるため、心理学的・脳科学的事実を頭に置いた上で、1つ1つ独立に検証していく必要があると述べられ、ご講演を締め括られました。
「子どもの最善の利益を考える国会勉強会」に参加して
「子どもが会いたくないと言っている」という言葉は、面会交流調停において、別居親と会わせない口実に使われていることはご存じのとおりです。
子の意見表明は大人が子の意見を知ることによって、子の利益につながる親子関係・父母の関係を構築する努力につながるものでなければならないし、子どもにとっては、大人が、自分の意見を聞き、自分を尊重してくれたとい経過が大切なのだと思います。
いやしくも、同居親の一方的な影響下(片親疎外等)のもとで、「正当な理由がない」のに、お父さんと会いたくない、お母さんと会いたくない等と意見表明をさせ、子ども自身に片方の親を捨てさせるような、過酷な、結果責任を子に負わせてはならないと改めて強く思わせる勉強会でした。