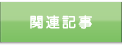【2011.05.25】 『子どもを救う「家庭力」 -臨床現場からの提言-』

『子どもを救う「家庭力」 -臨床現場からの提言-』須永 和宏 [著]
※画像をクリックするとオンライン書店(Amazon)のページが表示されます。
この本は、非行に走る子ども達の「生きづらさ」に焦点があてられている。私がこの本を取り上げたのは、我々の抱えている離婚後の親子交流問題と、かなり共通点があると感じたからである。この本を執筆している現代家族問題研究会では、近年失われつつある「家庭力」(父親力と母親力がより合わさった強靭な力)が子どもの豊かな育ちに欠かせないと捉え、様々な形でその分析をしている。
私達が、離婚後の親子交流に限定した形で、子どもの健全な成長に何が必要かということを念頭においているのに対し、現代家族問題研究会ではもう少し広い枠組みで、家族のあり方について研究しているというと、わかりやすいかもしれない。現代家族問題研究会のメンバーは、家裁の現職調査官や、元調査官でありながら、司法のあり方について大胆にメスをいれているところにも惹きつけられた。
本書は、複数の執筆者により、章ごとに単独に書かれているので、それぞれ簡単に紹介したい。
第Ⅰ部 子どもたちの危機と回復プロセス
第1章 生きづらい時代の子どもたち
-攻撃性の変貌と子どもたちのメンタリティ危機 須永 和宏
最近の少年の非行・犯罪の傾向や特徴について、動機の解明が難しくなってきた点と、突発的なものが増えてきた点を指摘している。重大事件を起こした少年のタイプを3つに分類しており、そのうちの一つが「表面上問題を感じさせることのなかったタイプ」である。そのタイプを、親との間で感情のこもったコミュニケーション体験が乏しく、自然の感情を伴った温かい人間同士の交流関係をほとんどもっていないと分析している。我々の経験している片親疎外に相通ずるものを感じた。
第2章 子どもたちの豊かな育ち
-思春期の問題行動から見た幼児期・学童期の大切さ 佐々木 光郎
父親の役割の重要性を説いている。父親には、自らも我が子と遊んだり、風呂に一緒に入ったりするなど、子どもとの身体的コミュニケーションをたくさんもつことが求められると。ところが、非行のある子どもの場合、こうした父親との体験がほとんどない。思春期になって家庭内暴力をふるう子どもの場合は、母親が強圧的に子どもを支配し、父親の影が薄い家庭になっているなどの例をあげ、父親の育児への参加の大切さを強調している。最後のコラムで、非行の予防薬は、「両親からの無条件に愛されること」と結んでいる。
第3章 地域社会に家庭を開く
-子どもの社会適応力を育てるために 川崎 末美
オートロック式の住環境で地域社会から孤立しやすい生活だったり、父親の存在が薄かったといったりといった環境による、現代の「母子カプセル」に危惧をいだいていることからこの章は始まる。父親参加型のコミュニティに属する子ども達が、他の地域の子ども達とどう異なるのか、定量的検証を試みているという点が、他の章とは少し趣が異なる。コミュニティに参加している父親のいる家庭では、母親による「きっちり」の子育てと、父親による「のびのび」の子育ての両方がうまく行われ、子ども達は高い自尊感情と、コミュニケーション能力を形成するという。本検証は、両親がそろった家庭でのケースであるが、離婚後の片親疎外により、自尊感情や基本的信頼間の低下を招くという調査結果と無関係ではないだろう。
第4章 子どもの回復過程(インタビュー)
-自立援助ホームで子どもたちと暮らして 三好 洋子
三好さんは、自立援助ホーム(青少年に暮らしの場所を提供する施設)で29年間寮母をしてこられた方で、須永さんからのインタビュー形式で話が展開されていく。自立援助ホームでの出来事が、ユニークでありながら含蓄のある言葉で表現されていて、惹きつけられる章になっている。本章に登場する言葉で、私が印象に残っているのは、「生きることと食べることは直結している。食卓から根源的な愛情交流が始まる」。子ども達との一緒の食事を妨害されることから、子どもとの切り離しが始まった私としては、非常に共感できるものとなった。
第Ⅱ部 少年による重大事件を読み解く
第1章 生活に色がなかった
-板橋両親殺害事件の刑事法廷から見えてきたもの 野口 のぶ子
野口さんは、元家裁調査官である。この章は、どうしても読んでもらいたい。何故なら、我々が対する家裁調査官とは、まるで異質の調査官がいる。このような洞察力と発言力をもった調査官が、家事を担当しているのなら、片親疎外という言葉を持ち出すこともなく、何が本質なのかきちんと見極めてくれるだろうと期待を寄せたくなる程である。痛烈に司法のあり方を批判しているその姿を、今の家事調査官には期待すべくもなく、それだけに私はこの章を読んで感動した。野口さんはすごいと。
第2章 学生たちがうけとめた「板橋事件」と「少年法」
-「司法福祉」講義のレポートを手がかりとして 田中 敏政
一つの事件を題材にして、学生たちとともに考える、そんな構成のところどころに、調査官としての信念が垣間見れる(私たちが目にする家事調査官があまりにひどいので、そう感じるのかもしれないが)。子どもは親に見捨てられては生きていけず、子はどんな状況におかれても、親のなすまま「忍従」するしかない点を、裁判官は全く取り上げなかったことを不合理で不自然と多くの生徒ですら感じている。そんな事例を引き出しながら、裁判官の言動に疑問を投げかけている。これは、まさに私たちが感じる裁判官像と同じであった。
私達が接するほとんどの家裁調査官は、子どもの最善の利益を大凡真剣に考えていない、あるいは考えていたとしても、最終的には子どもの最善の利益を二の次にしてしまう、他の先進国と比して、人間関係諸科学の専門家というのにはあまりに恥ずかしいような役人でしかない。しかし、この本を読んで、真の意味で「子どもの成長」を考え、提言し、行動している調査官がいることを知り驚いた。こうした家裁の人たちが特殊であることが、何とも情けない国であるが、一刻も早く、真の専門家が、リードする国になってもらいたいと強く感じた。